中編文画1-3 言葉は噓を吐き、行動は真実を語るの続きの続き
4
ジーパンにミッ〇ーのTシャツ、髪は後ろで黒ゴムでまとめてポニーテール、化粧は目元だけという自分史上もっともラフな格好でスマホのグーグルマップを見ながら行ったら、相手もジーパンに黒Tにジーンズ地のエプロン、つんつん立った伸びかけの坊主頭という負けず劣らずのラフな感じだった。ひどく痩せていて、目が大きく背が高い。年はだいたい四十くらいといったところだろうか。
「じゃ、ちょっとそちらへ」

部屋はだいたい二十から二十五畳くらいで、壁際の棚におもちゃとかレゴブロックなんかが置いてあって真ん中ら辺に低いテーブルがいくつかとテレビが置いてある。
左奥のテーブルに案内され、わたしは広田と向かいあって座った。
「こちらの責任者をさせていただいております広田と申します」
エプロンについた名札をつまんでわたしに見せながらそう言った。
「吉田です。よろしくお願いします」
わたしはそう頭を下げた。
「じゃ、すみません。履歴書を」
「はい」と私は頷き、自分のトートバッグの中を漁った。
「あれ? あれあれあれ?」
「どうされましたか?」
「ない。え?」
さらに焦ったふりをしてがさごそまたバッグを漁る。
「書いたのに。昨日の夜書いたのにー!」
「あ、忘れてきちゃったんですかね?」
「あっ、もう! あそこだ。テーブルの上!」
そう言ってわたしは頭を掻きむしり、目を閉じて長いため息を吐いた。
「あ、じゃあ今度でいいです。履歴書はまあ、しょせん履歴書なので」
「すみません。取りに帰るとか……」
「あ、いいですいいです」と広田はかぶりを振った。「お話を聞ければあれなので。でも事務的なのでいるので、まあ、今度で。ご縁があればというまあ、そういうあれですが」
わたしは「すみませぇん」と言って、広田の顔をじっと見る、イケメンでもブサメンでもない。マスクで顔の下半分が隠れているから微妙だ。
「じゃあ、どうしましょうか。一応面接ってことなので、まずはこちらからここのお仕事のざっとしたことをお伝えしましょうか」
広田はあしを崩しかけてやめて、背筋をピンと伸ばしながらそう言った。
「あ、はい」と、わたしは頷く。

「まあ、ホームページとかもご覧になっているか知りませんが、まあいわゆる学童です。子供のことを見るのが仕事の九割です。見るっていうのは、怪我や喧嘩をしないように見守ったり、宿題の分からないところを教えてあげたり、遊びの相手をしてあげたりという感じです。あと、掃除とかお迎えとか事務的なこともありますが、まずは子供を見るということですね。それが主な仕事内容になります」
「見る……、ですか」
「ええ。話を聞いてあげるっていうのもあります。相手をすることですね。ここは家と学校の中間的なところですので、親御さんたちが迎えに来るまでお父さんお母さんや学校の先生の代わりに子供たちを『見る』んです」
分かったような分からないような説明だ。
「まあ、やってみりゃ分かります。っていうか、やってみないと分かりません。習うより慣れよってやつですね。以上です」
「はあ」とわたしは答え、マスクの上の広田の目を見た。
「じゃあ、次は吉田さんの番です。絶望したとかそういうことをお電話では仰られていたかと思うんですが」
ああ、そんなこと言ったかな。
「え、まあ、っていうかわたしもうすぐ結婚するんです」
すると、広田は頭をのけぞらして大袈裟に驚いた。
「えっ、あっ、おめでとうございます」
「あっ、は、ありがとうございます」
わたしは小さく頭を下げる。
「え、じゃあなんで絶望なんですか? ご結婚とか幸せじゃないんですか?」
「あー、まあちょっとワケがあって、っていうのはその彼には奥さんと娘さんがいて、でもその奥さんとはだいぶ前からうまくいってなくて、もうすぐ離婚して、わたしも大学卒業するからそのタイミングで結婚しようってことになってるんです」
「えっ、ああ、大学生なんだ」
フリーターかなにかと思っていたようだ。
「そう、でも離婚してくれるかどうか微妙で、わたしも大学ぜんぜん行ってないから、五年生になるの確定で、五年生で卒業できるかどうかも微妙で六年生になっちゃうかもしれなくて」
「離婚するか微妙ってことは、嘘吐いてるかもしれないってこと?」
「はい」と私は正直に頷いた。

「お互い嘘吐きあってるんです。ひどいですよね。なんなんですかね、人間って」
すると、広田は笑った。
「じゃあ、嘘吐かなきゃいいじゃん。少なくとも吉田さんはさ」
「好きで吐いてるわけじゃないですよ。吐かざるをえないから吐いてるんです」
「そうなんだ。相手が望む答えを言っちゃってるってこと?」
ああ、そういうことか。
「まあ、好きだし、嫌われたくないから」
こいつは何にも分かってないなと思いながら、わたしはそう答えた。
「え、でもずっと嘘吐き続けるわけにはいかないでしょ。いつかは本当のことというか地を出さなきゃいけなくなる」
んなことは、あんたに言われなくても分かっている。
「できないから悩んでるんです。できたら、とっくにやってますよ」
すると、広田はぴくりと眉毛を動かし、眉間の間に皴を作った。
「それもそうですね。失礼しました」
結局その場で採用ということになり、とりあえず週三日、人の足りない月、水、金の二時から六時の勤務とシフトまで決まった。
大学の方は大丈夫なのと訊かれたが、行ってないから大丈夫と答えた。
「でも、卒業するんでしょ?」
「分からないです。もう、心が折れちゃってるんで」
すると、フッと鼻で笑われた。
「じゃあ、辞めちゃえばいいじゃない」
「いえ、そうすると仕送り止められちゃうんで」
「あ、そっか。じゃあ続けなきゃだね」
案外、ものわかりのいい人のようだ。
詳しくは来週の月曜で、と話に片がつき、わたしは「りく」を後にした。
コンビニでツナマヨおにぎりとレタスサンドを買って帰り、それらで腹を満たしつつ、履歴書はどうしようか、そもそも来週の月曜からお願いしますと言っちゃったが、本当に行くのかどうかとかをぐるぐる考えた。
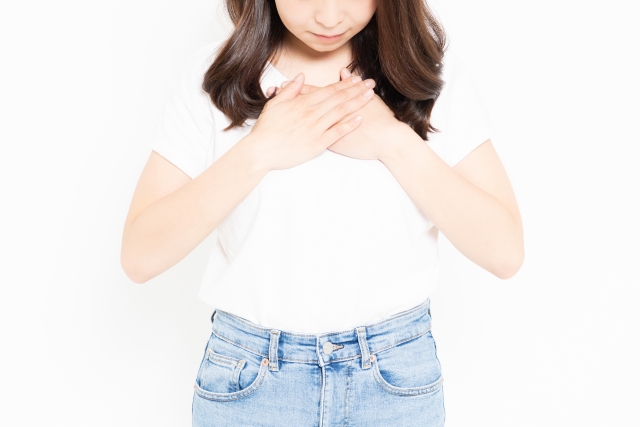
あの広田という男が信用できるかどうかは微妙なところだった。面接中もわたしの胸元を幾度となく見ていたし、帰り際靴を履くときには突き出した尻を超ガン見していた。きっと頭の中はエロいことでいっぱいで、さっそくわたしも今晩のオナニーのおかずにされることだろう。
でも、エロいからといって悪い人なわけではないし、エロいかエロくないかというより、隠すのが上手いか上手くないかの問題な気もする。広田は、上手くないを通り越して下手だ。あれでは大抵の女が気づく。あ、こいつ見てるぞ、と。あれでもうちょっと不細工かキモデブとかだったら、女は絶対に近づかないだろう。顔とスタイルがそこそこだから、まあいっかということでそれで生きてこられた。そう考えると外見というのはやはり重要なんだなと思う。同じことをしても、OKかNGかは外見で決まる。
まあ、いっか。履歴書はずっと忘れ続ければいいし、行くか行かないかは当日の気分で決めよう。
──バイトすることになったよー。来週の月曜から。
わたしはさっそく正直にラインを送った。十五分後に既読がつき、返事がかえってきた。
──え、ほほちゃんが? なに? どこ?
バカにされているような気もしたが、そんなことは気にしない。
──近所の学童。「りく」ってとこ。
──学童? なにそれ?
世代的に知らないのだろう。
──放課後の小学生預かるところだよ。共働きの家の。
──へー、よく知らないけど。っていうか大学もう大丈夫なの?
わたしは間を置かずこう打ち込んだ。
──うん。もう単位取り切ってるから大丈夫。今年は微妙だけど、来年は卒業できると思う。
既読がなかなかつかず、それは通知だけを見て既読をわざとつけずに考えているのだなと分かる間だった。その隙にわたしはトイレに行き、やけに黄色い小便が出てすっきりしたところで返事がかえってきた。
──じゃあさ、ほほちゃんが卒業したら離婚するよ。そしたら晴れて結婚すりゃいいじゃん。

返事を打てずに呆然としていると、続けざまこう送られてきた。
──それでみんなハッピーだよ。
わたしが卒業できないことを見越して、面倒なことを一気に片付けにかかっているのだ。いまの性生活と危ないゲームを続ける関係を保ちつつ、自分は実害を受けないところまで避難する。
──そうだね。ウィンウィンだね。
と、わたしは送った。
──じゃあ、それで。 来週からのバイトがんばってね。
──うん、ありがとう。
バイトどころではない。卒業しないと離婚も結婚もなくなってしまった。その結構重大な約束をいまラインでしてしまった。
バカなんだよな。わたしってほんとバカなんだよ。死にたくなる。
入学できたんだから卒業もできるだろうと思うのだが、ぜんぜん行ってなくていま何がどうなっているのか分からないし、もう全部むちゃくちゃに踏み倒しちゃっているから、どうしようもないのだ。
わたしが卒業して、正直が離婚して、わたしたちが結婚する。
これは前々から正直が企んでいて、言い出すタイミングを見計らっていたのだ。オムツごっことかそんなことをやっている時点で、本気とか恋愛とか愛情とかそんなんじゃないことは分かり切っていたし、でもそんな変態的感覚を共有してるっていうのはやっぱりゾクゾクするし、それはどこまでいっても性欲でしかないのかもしれないけれど、それはそれで何が悪いのだろう。
つづく(予定)