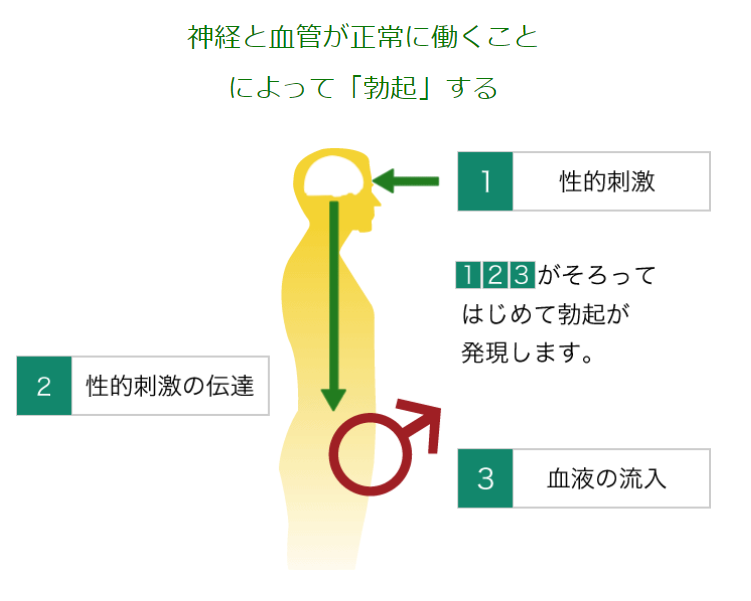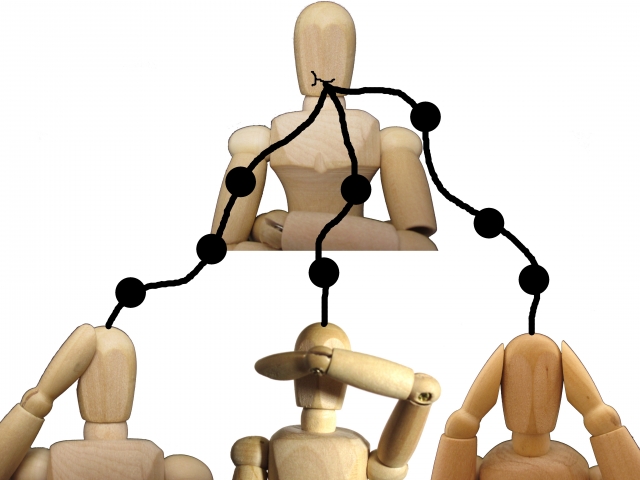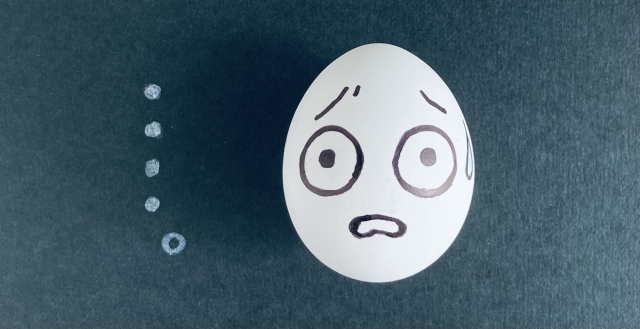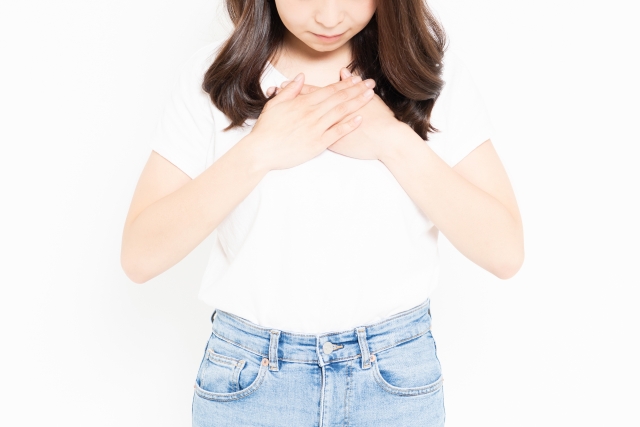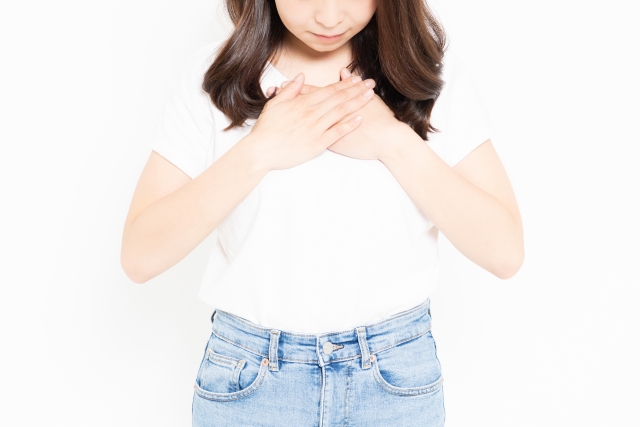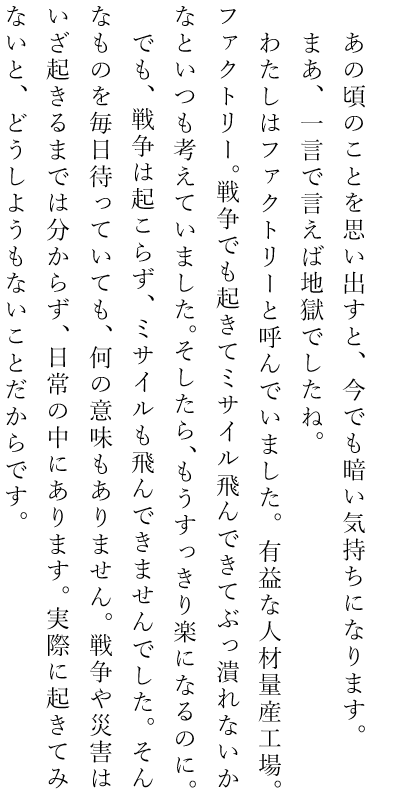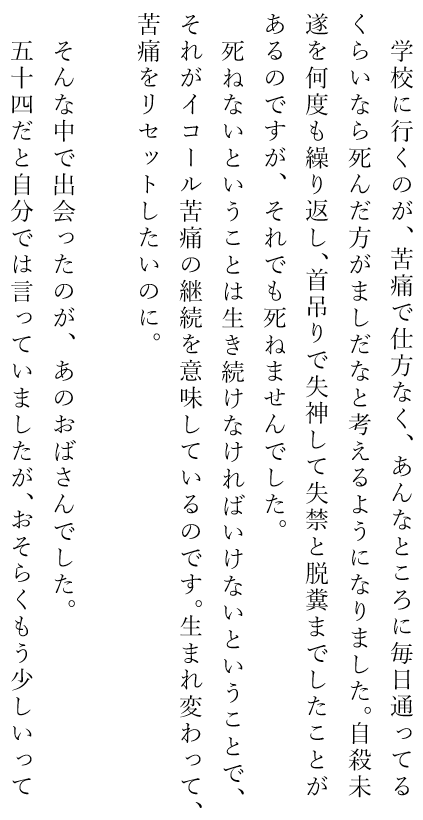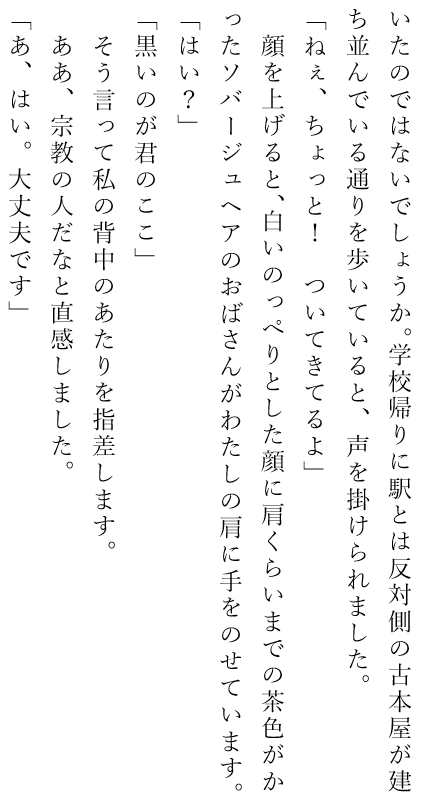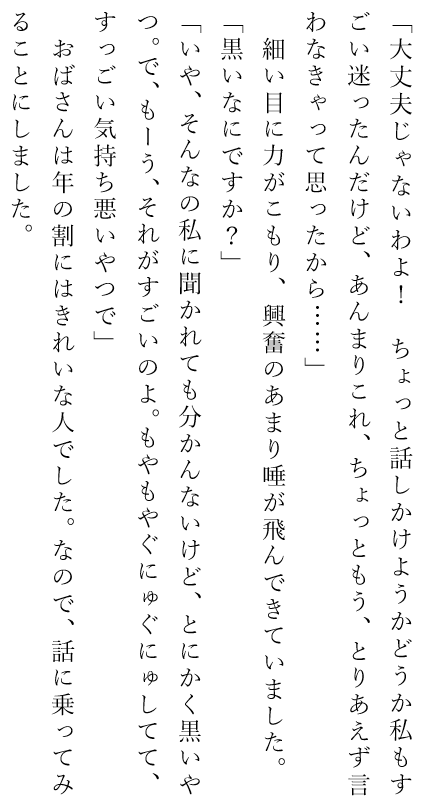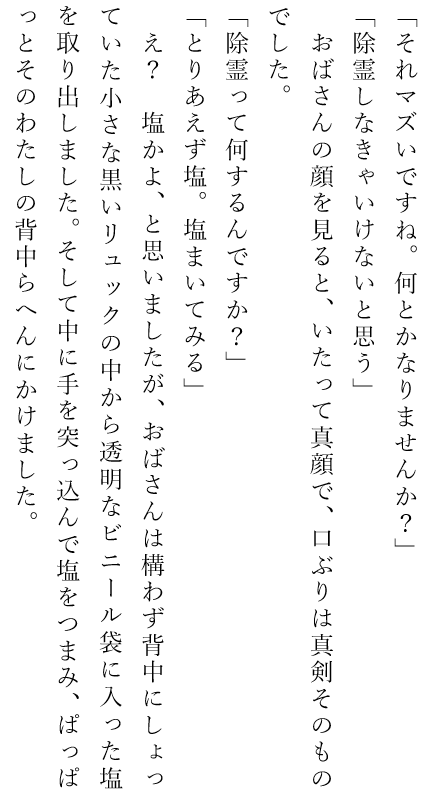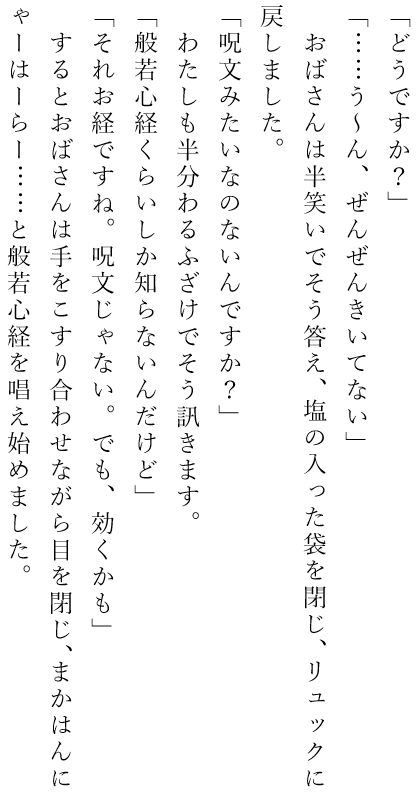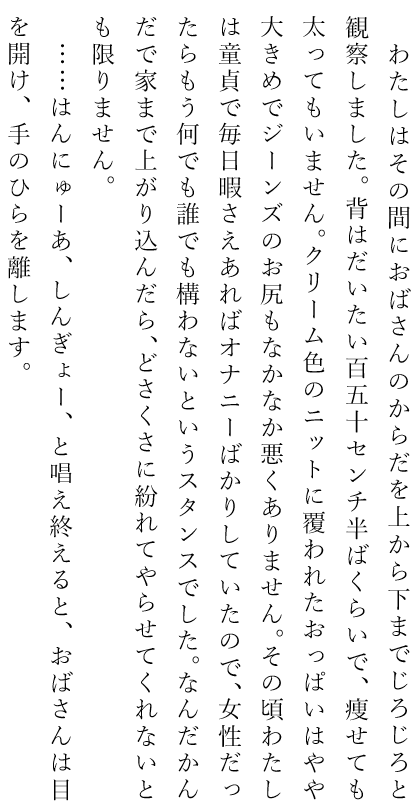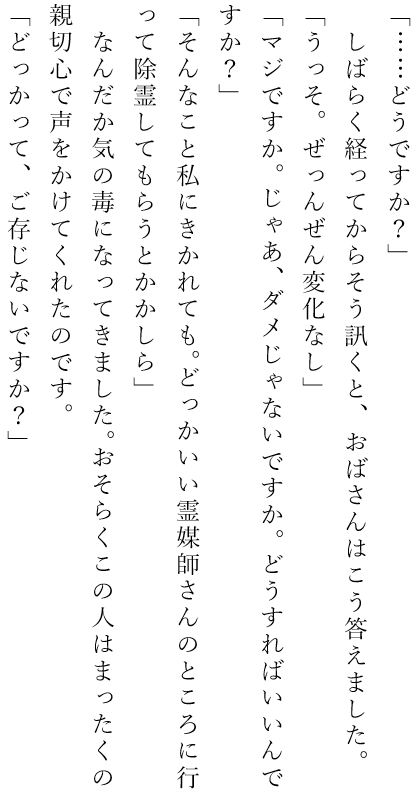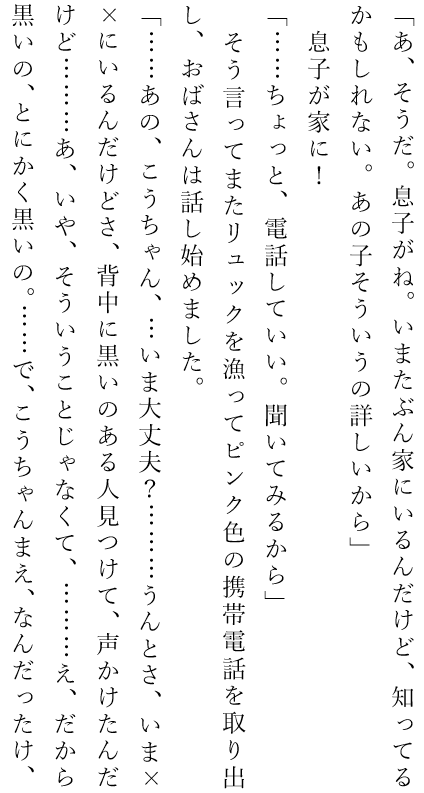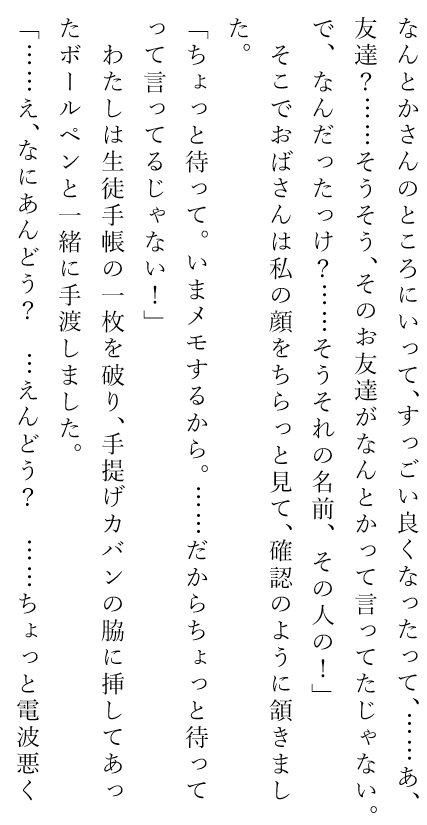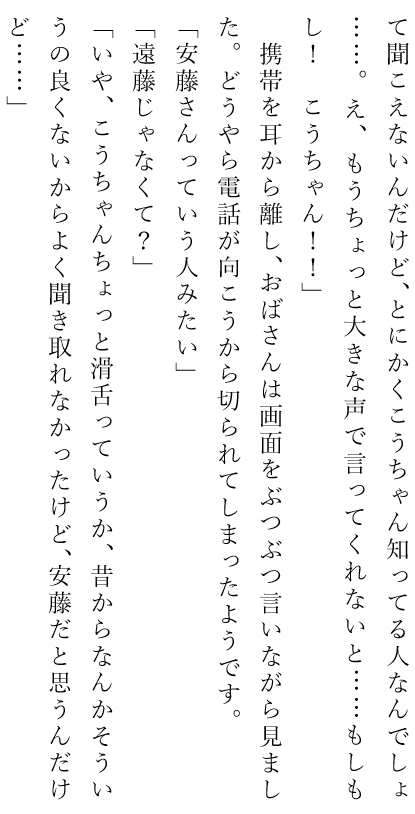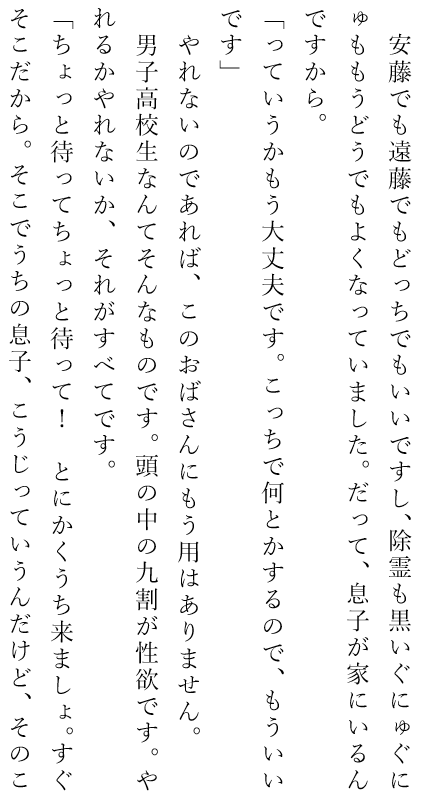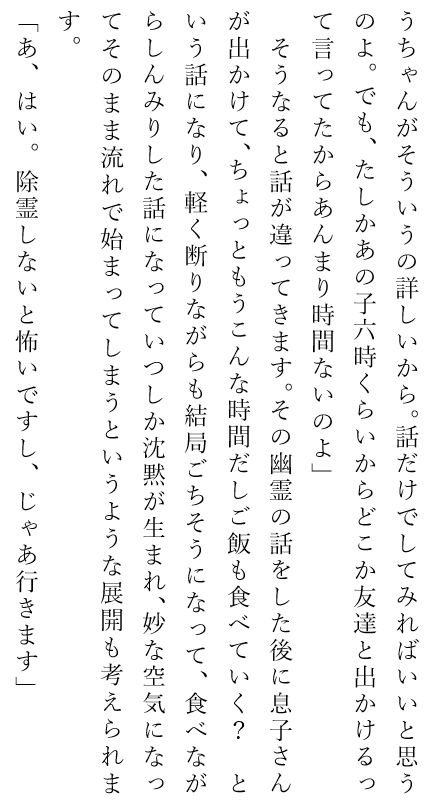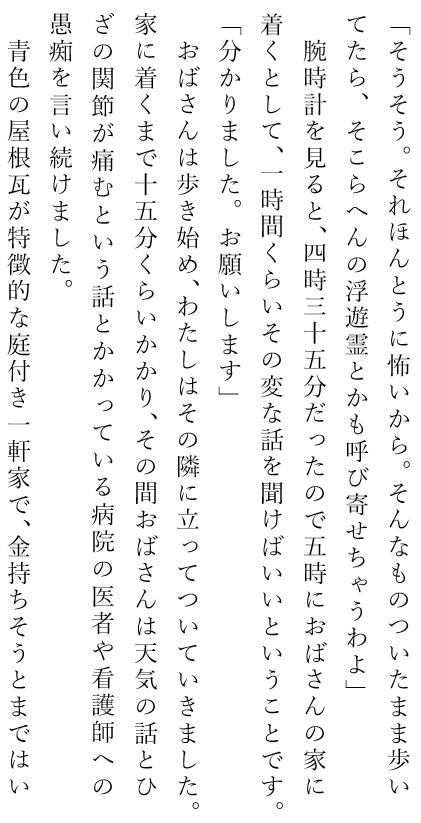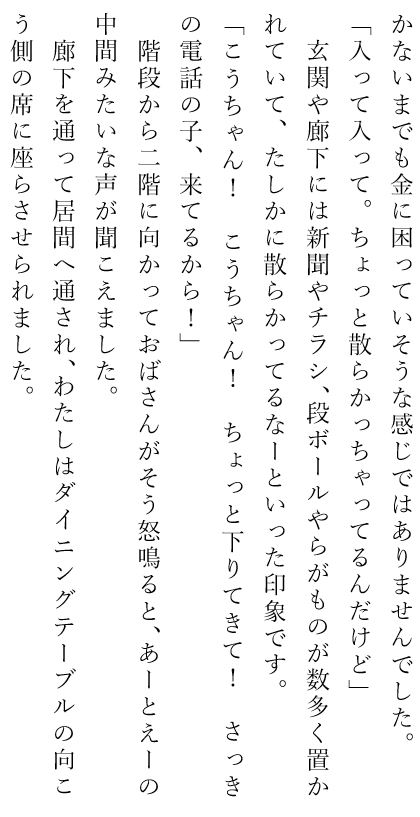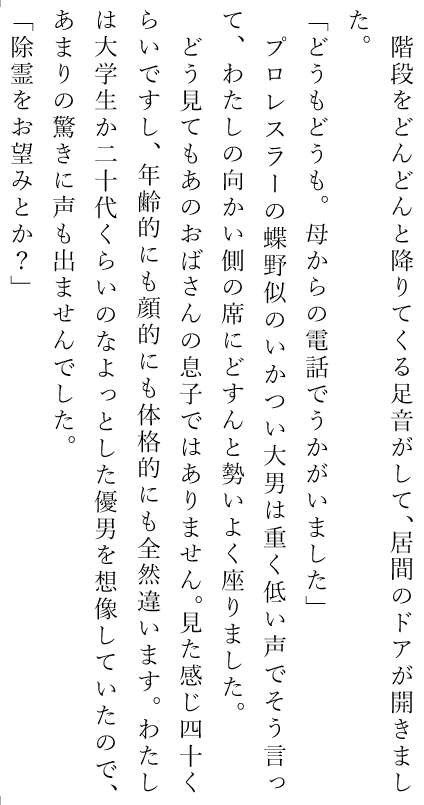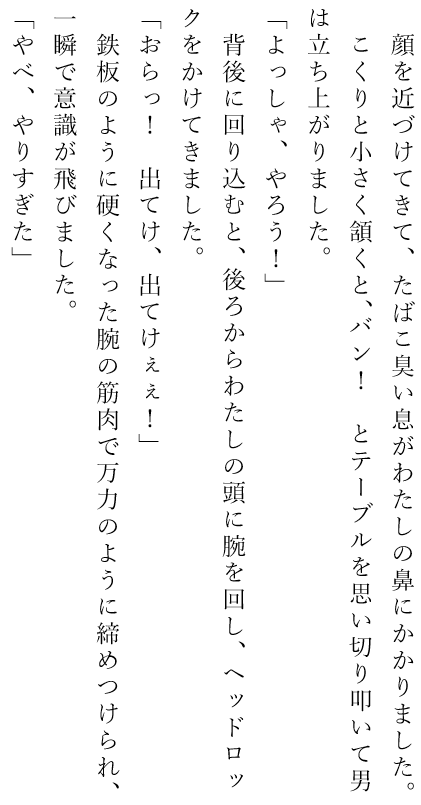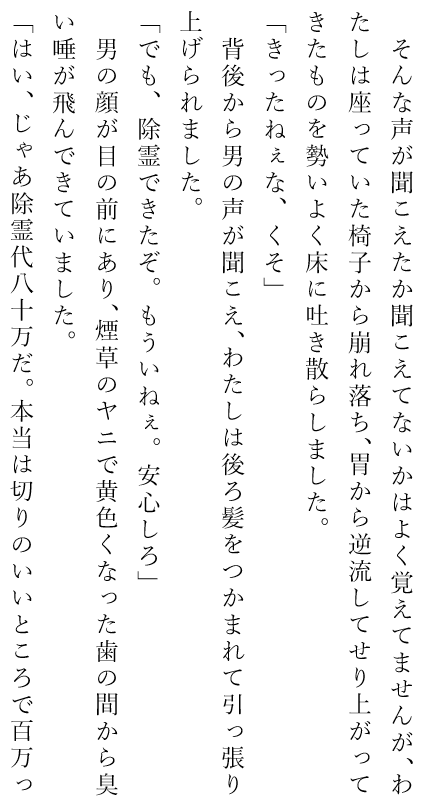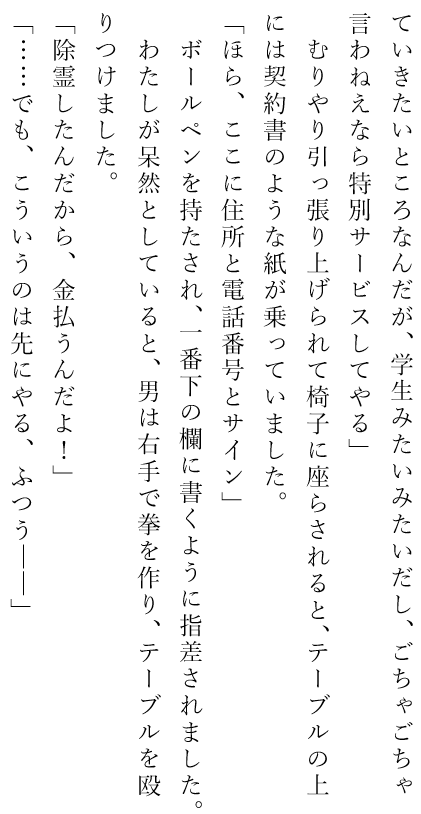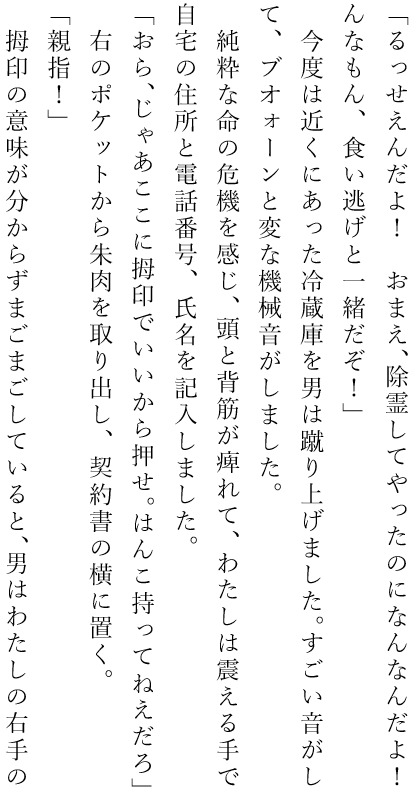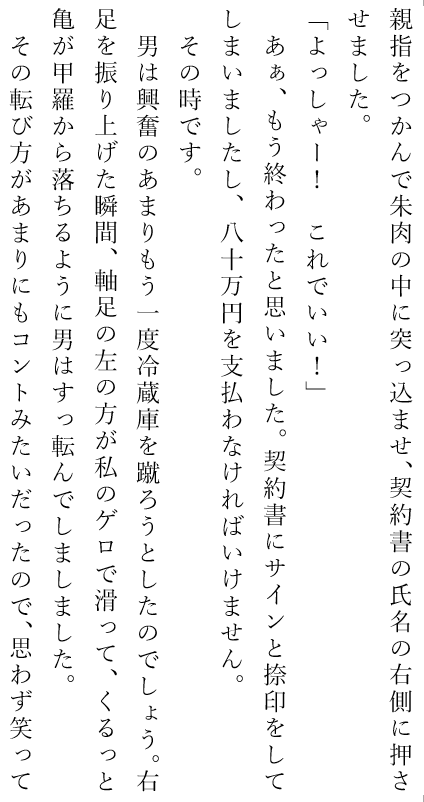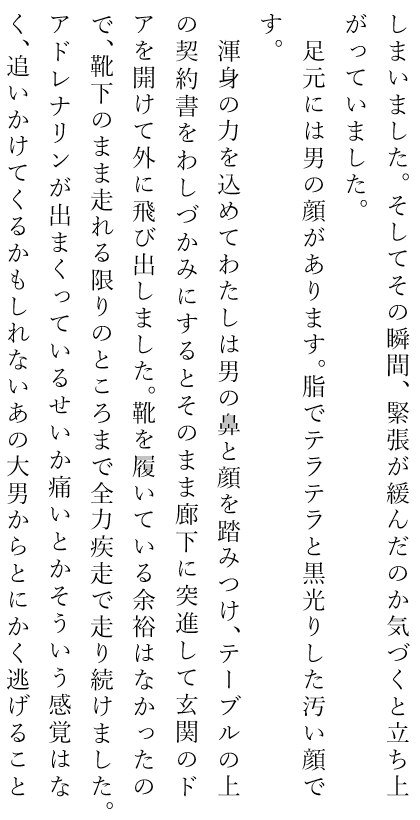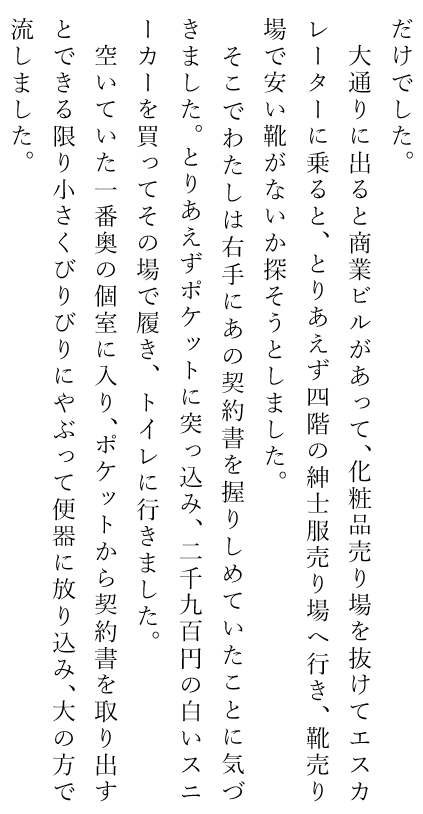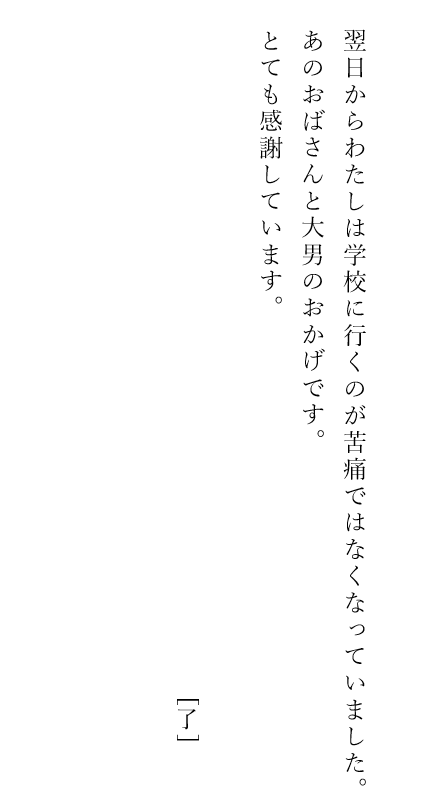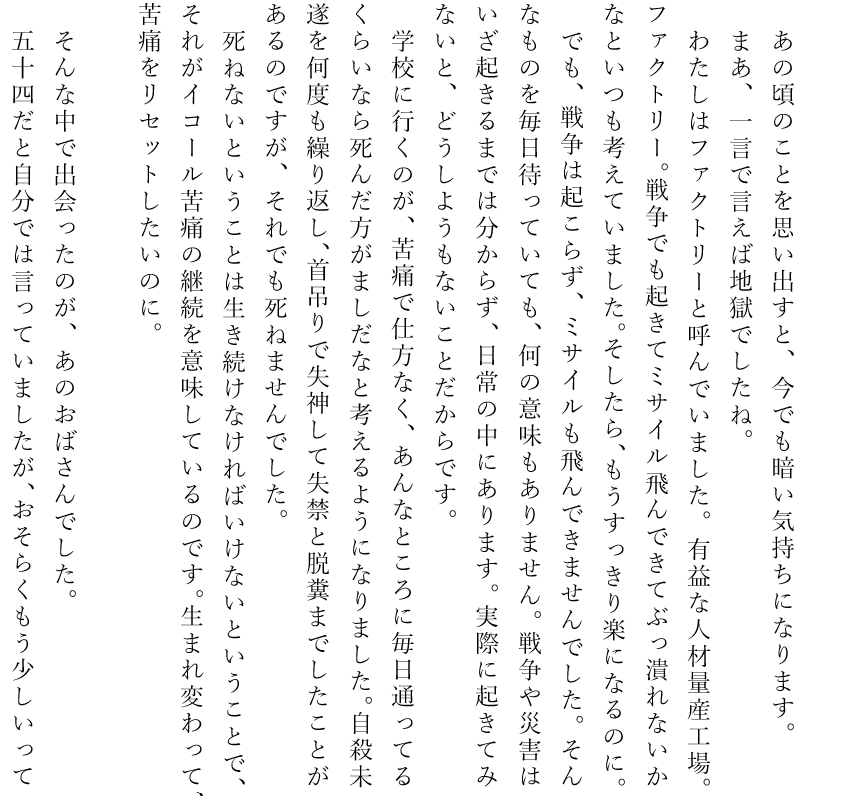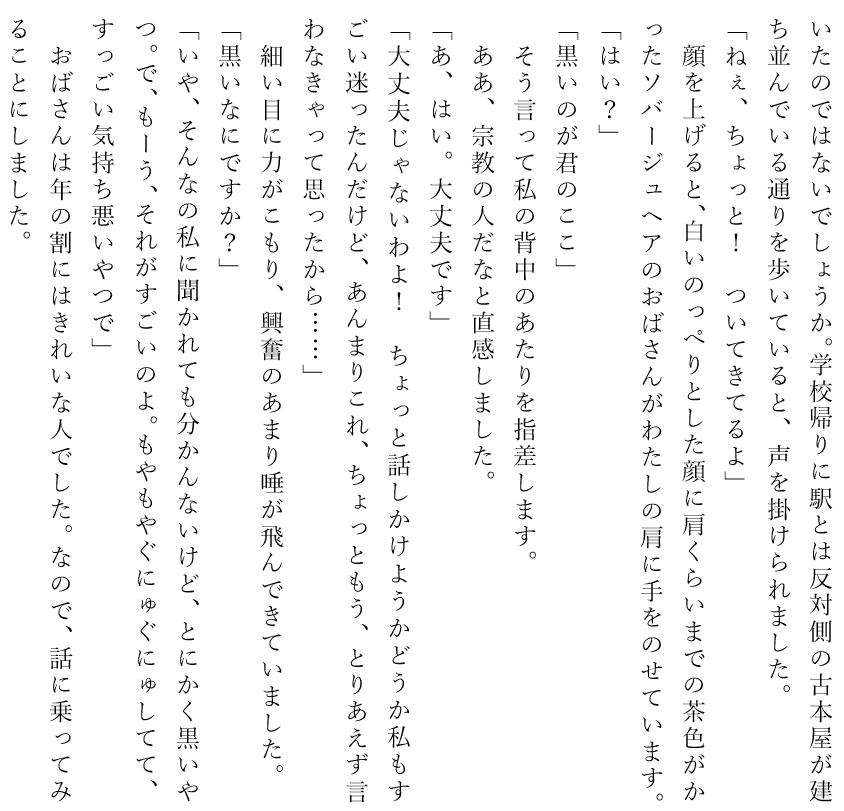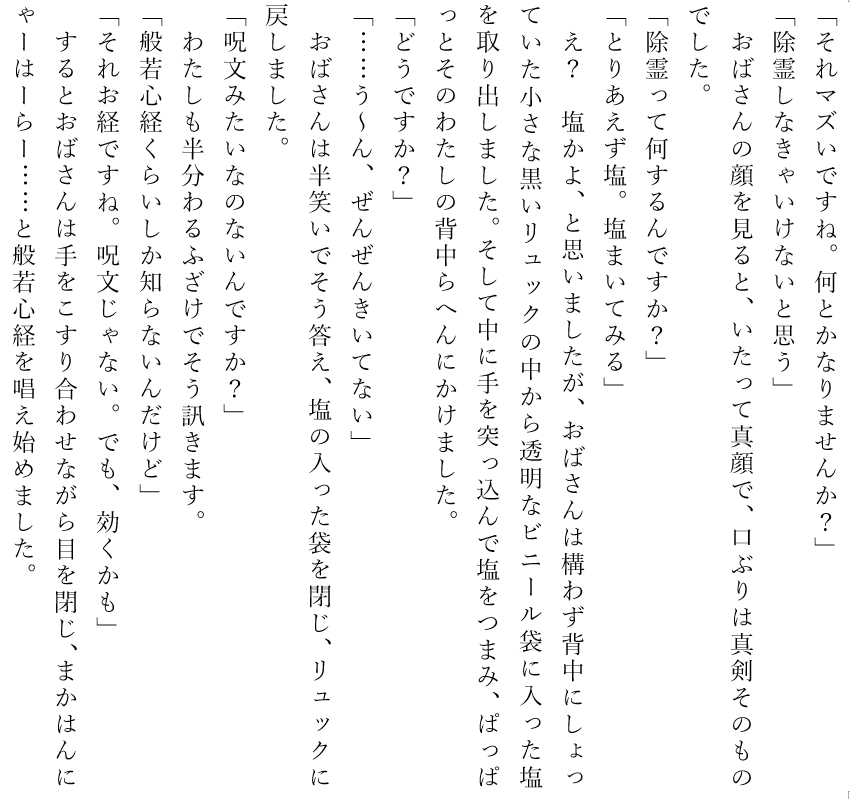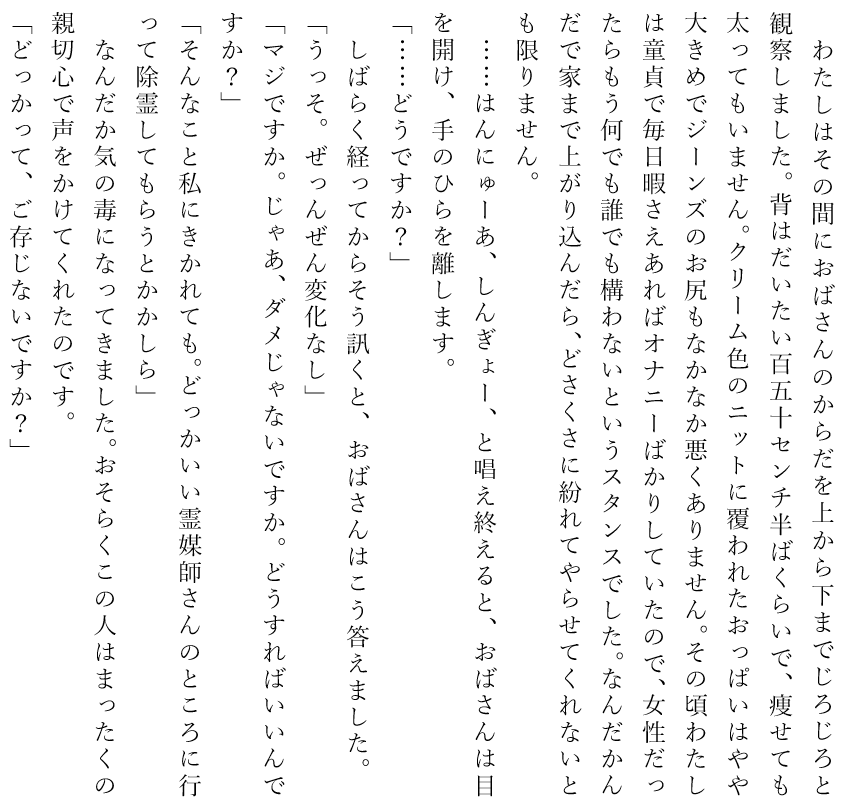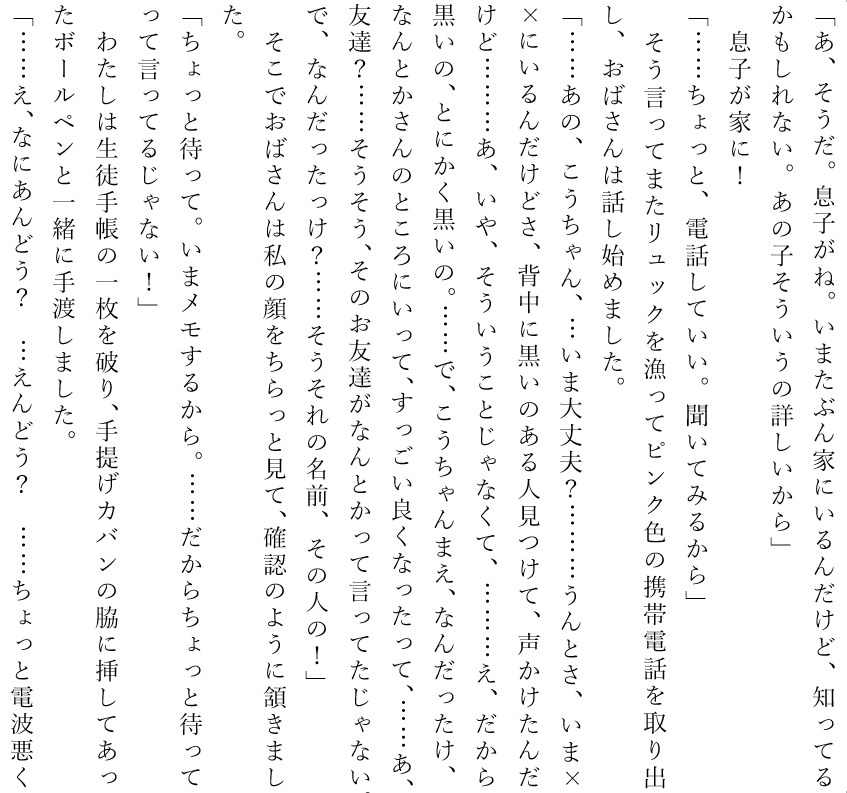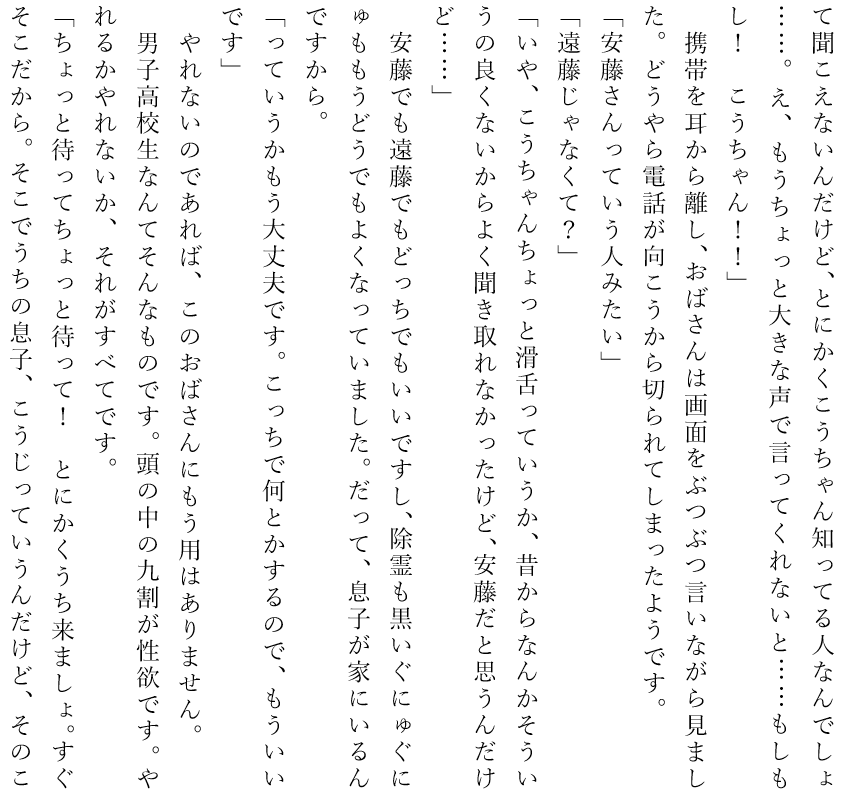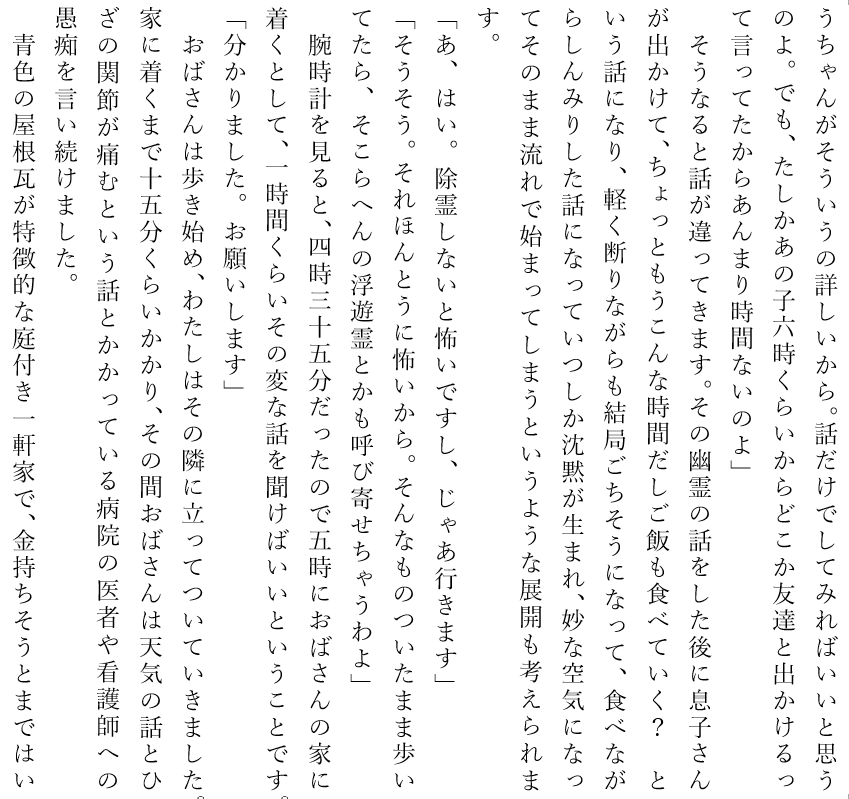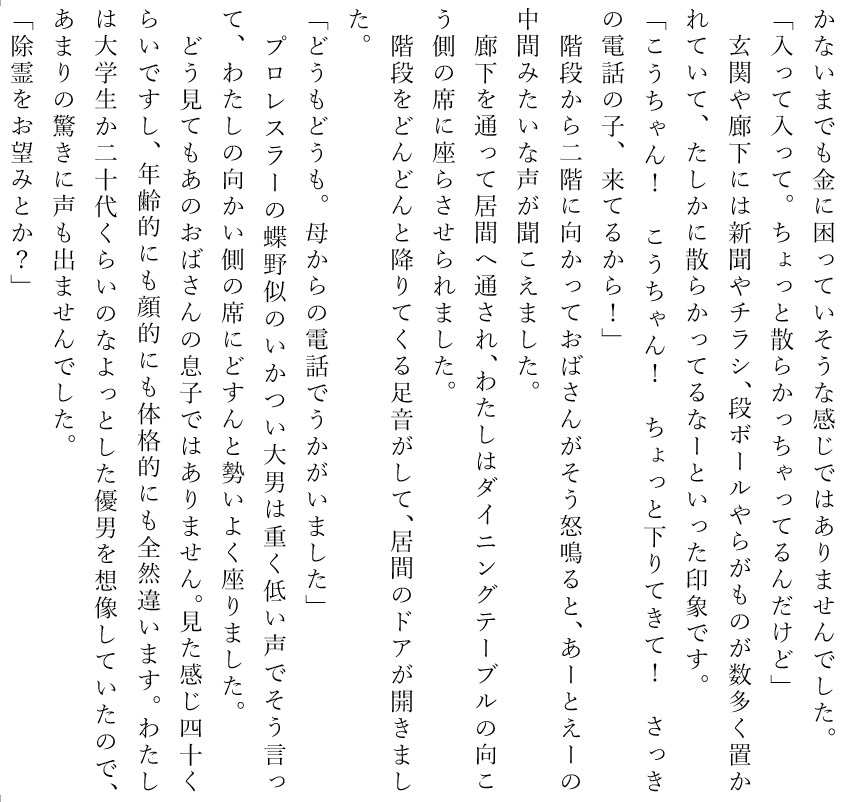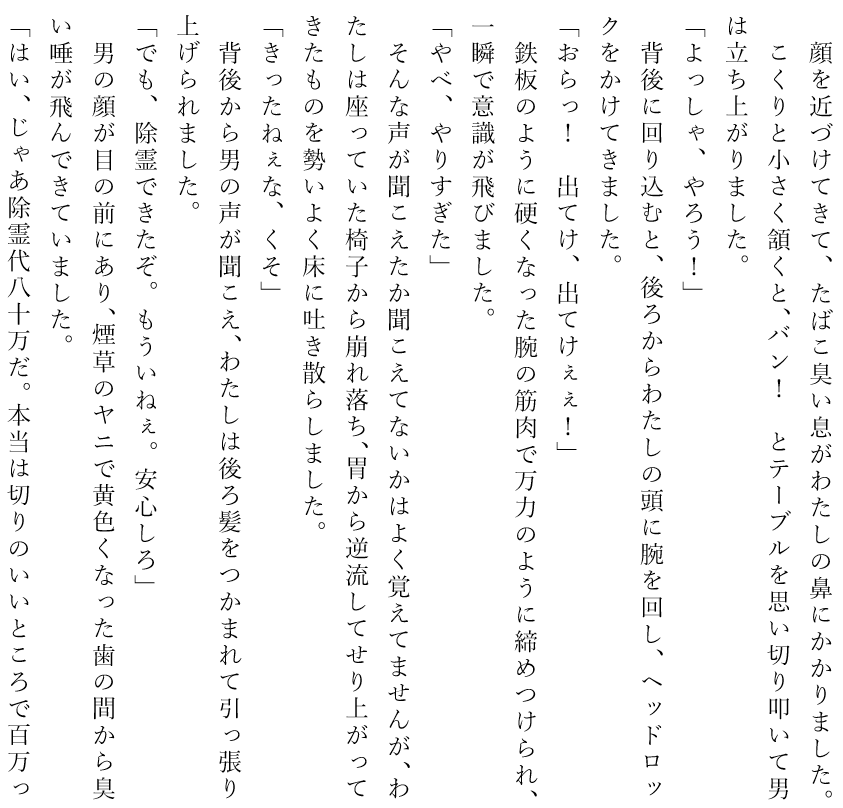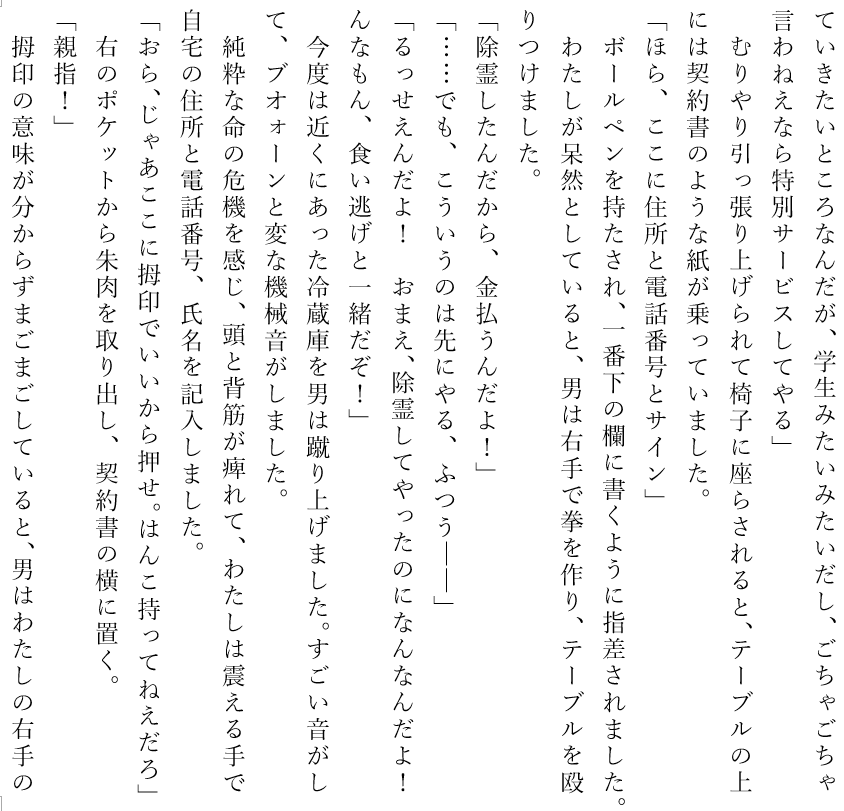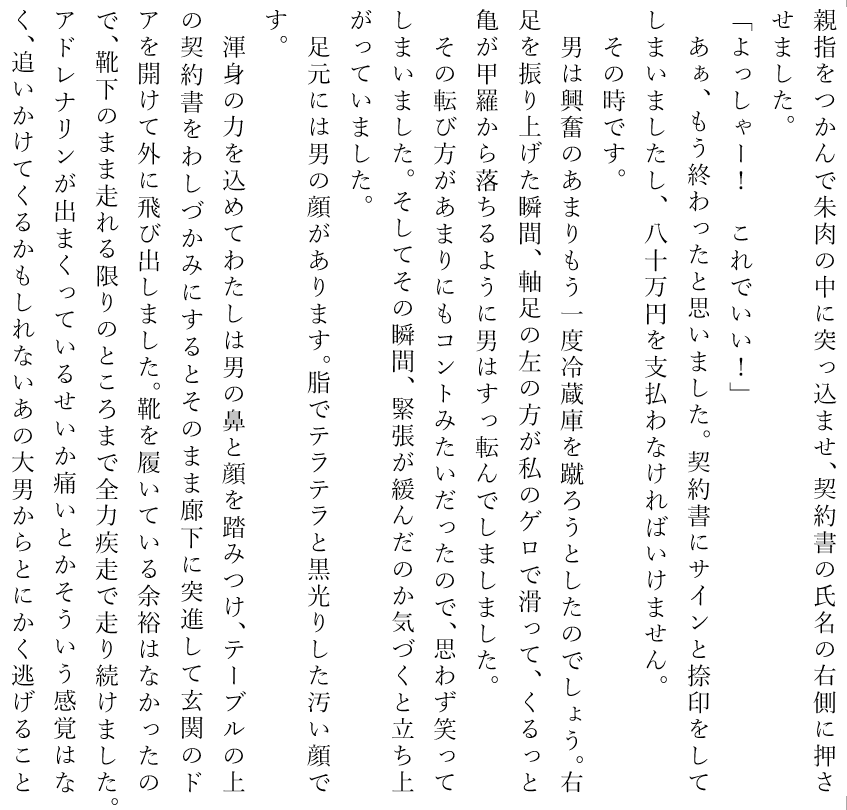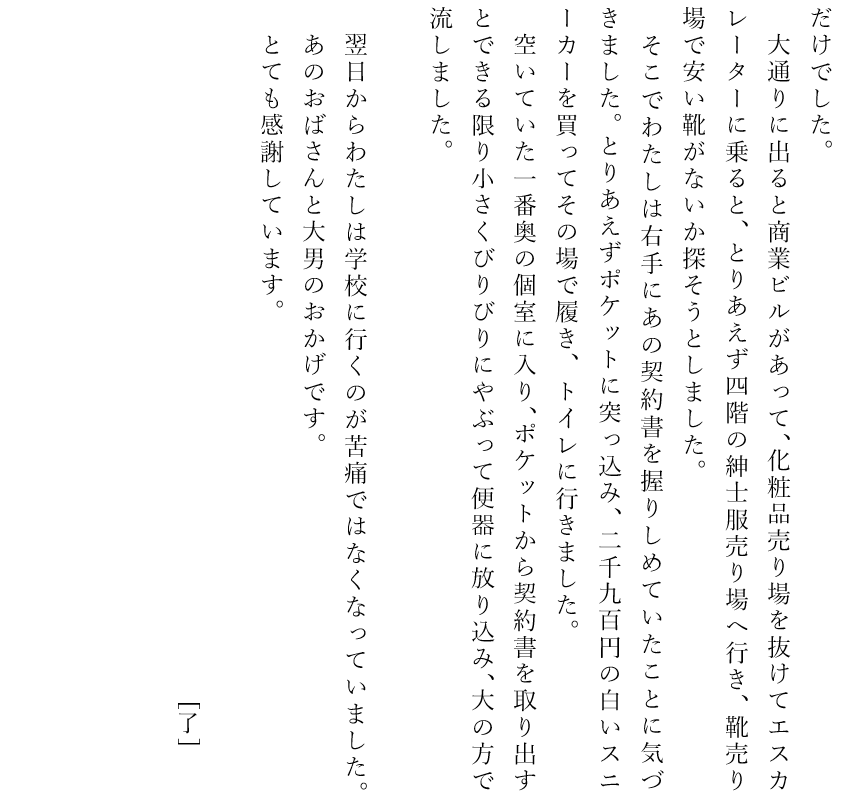1
ああ、またやってしまった。
ヴァギナから伝う白い粘液を右手の指先で伸ばしながら、わたしはひどく後悔していた。
そもそもどこから間違ってしまったのだろう。よく覚えていない。何となく声をかけられて、面白そう人だなと思って一緒に飲んで帰ってきて、やって寝て起きたらその人はいなくなっていた。しかも昨日は危険日だったのに中出しされてしまった。連絡先も交換していないからどこの誰だかも分からない。

わたしには結婚を約束した彼がいる。わたしより十個上の三十三歳で既婚者、三歳になる息子さんと奥さんがいて、離婚に向けて話し合いをしているところだ。大学卒業と同時に結婚する予定だから就職活動とかはしていない。結婚したら家庭に入って専業主婦になるか、どこかパートにでも出るつもりだ。
冷蔵庫に入っていたミネラルウォーターを飲み、わたしは昨日寝た男の顔を思い出そうとする。でもそれは曖昧なイメージが浮かぶだけで像を結ばず、声だけが記憶の端の方に残っている。
「それってさあ、ヤバくない?」
おそらく口癖なのだろうがこの言葉を何度かわたしは耳にしていて、その軽薄な口調が男の頭の悪さを物語っていた。
外に出すと言っていたはずなのだが、結局男はペニスを最後まで抜かず、残らず中に出し切った。ああ、やられたとわたしは思ったのだが、頭が快感で麻痺していてうまく働かなかった。
「ああ、気持ちよかった」
男は勢いよくペニスを引き抜き、感想を口にした。
「ちょっと中に出さないって言ったじゃん」
「あぁ、ミスった。ごめん」
絶対に嘘だった。抜く気なんてさらさらなかったのだ。中で全部出し切ってやろうという強い意志が、男が股間を押しつけてくるその力に込められていた。
「まじ最悪なんだけど、これ妊娠してたらどうするよ?」
「よーく洗っときゃ大丈夫。精子なんて流れるって」
そんな会話をしてるうちに眠くなってきて、いつの間にか寝落ちしていた。で、起きたら一人。男の痕跡は消されていて、わたしのびらびらの中の白い精液だけが唯一の残留物ってわけ。
──おはよう。来月ほほちゃんの誕生日だと思うんだけど、なんかほしいものある?

スマホが鳴って、見ると藤島正直からそんなラインが届いていた。正直と書いて「まさなお」と読む。ほほというのはわたしの名前で、「帆々」と書く。帆船のように風に乗ってまっすぐに突き進んでいくという意味を込めたらしい。お母さんが言っていた。まっすぐかどうかは知らないが、とにかく突き進んでいってはいる。
──ちょっと寝起きで思いつかない。考えてまたラインするね。
左手でティッシュを取ってびらびらを拭いながら、右手でそう打ち込んで送った。
すぐに既読がつき、よく見るクマの陽気なスタンプが送られてくる。
ティッシュの繊維がびらびらにくっつき、白いこよりのようなものがいくつかできる。ああ、面倒くさいな。時間が経って精液が乾いてねちゃねちゃになってこびりついてて、取れなくなってる。
来週の土曜日に高崎に住んでいる向こうのご両親に挨拶をすることになっている。こっちの両親にはまだ言えていない。既婚者だの子供がいるだのと言えば、絶対反対するに決まっている。お母さんは泣くだろうし、お父さんは顔を真っ赤にして酒を飲んで怒鳴る。だから言いたくないし、言えない。
あぁ、もう死にたい。生きていてもいいことなんて何もない。
トイレに行って最終的にビデで洗い流し、うんこをする。三日ぶりくらいだ。こんなにすっきり出たのは。バナナ二本分くらいが、ずるずると出た。昨日バックでかなり激しく長く突かれたからだろう。そこで尻だか腸の中の固まっていたうんこがほぐれて出やすくなったのだ。そう考えると悪くない。便秘の時はバックで突きまくってもらえばいいのだ。そうすれば便秘も解消するし一石二鳥だが、あまりにも効き過ぎると、イったときに出てしまう気がする。そんな場合、男はどうなのだろうか。イきながらうんこを漏らさせたら、とにかく大変なことになってしまうことだけは確実だ。おしっこくらいだったらいいだろうが、うんこだとどうなるのだろうか。どこまでが興奮してどこからドン引きするのか、そのギリギリラインがどこにあるのかがちょっとよく分からない。

そういえば、よく正直とするのが、おむつプレイだ。これはセックスの時に赤ちゃんごっこをするわけではなくて、大人の介護用のおむつを買ってきてそれをわたしが履いて、コンビニでレジのお会計中に漏らすというものだ。漏らすタイミングは正直から指示が来る。ちょっと離れた場所から見守っていて、ラインに「うんこ」とか「おしっこやや多め」とか指示が来て、スイカでとかペイペイでとか店員さんに言っている最中に指示通り漏らすのだ。でもわたしは便秘気味なので、おしっこの方は大丈夫なのだが、うんこが指示通り出せずにいつもイキんで終わりか、出たか出てないかくらいしか出せない。最悪の場合、長めの屁が出て終わりというパターンもある。それを見ながら正直はニヤニヤして股間をモッコリさせている。わたしも背徳感と公衆の面前で漏らしている恥ずかしさで頭がトロトロになって、乳首が固くなり、子宮がキューッとなる。皆の視線が密かに現在進行形でお漏らし中のわたしに突き刺さり、子供たちの甲高い声が店の中に響いている。
まあ、そんなことを二人でよくしている。いい年こいた大人が、恥ずかしげもなく。
うんこがすっきり出ると死にたいという気持ちもけっこうすっきり晴れていて、あぁ、ただの便秘だったのだなと思い知らされる。生きていてもいいんだなと感じる。
2
正直からラインが来て、高崎行きが延期になったという。理由はお父さんの血圧が上がったから。それが嘘だということはわたしでなくても誰にでも分かっていたことだけれど、とにかくOKと返事をしておいた。
離婚もしてないのに、挨拶なんてできるわけがねえだろ。
そんなことはもう分かって分かって分かり切っていたのだけれど、正直がそんなことを言い出すからわたしはそれに付き合ってあげなければいけなかった。で、どうするのかと思えば案の定延期。いったい何がしたいのかさっぱり分からないのだけれど、正直なりの何だかよく知らない理由があったのだと思う。わたしが喜ぶとか、離婚が実際は成立していないのだけれど既成事実化するとか考えたのではないだろうか。

「もうすぐ離婚するから結婚しよう」
「じゃあ、わたしももうすぐ卒業するからそのタイミングで」
ラインでそんなやりとりをしてから数ヶ月が経つ。
お互い嘘ばかりだ。大学なんて一生懸命勉強して二浪して入ったはいいけど、バカらしくなって途中から全然行かなくなり、単位も取れていないから卒業なんてできるわけがない。一緒の年に入った子たちはこの春で卒業だけど、わたしは五年生になることが決まっているばかりか六年生で卒業できるかもあやしい。七年生とか八年生まではいけるらしいが、そこで自動的に除籍になるらしい。おばさん大学生っていうのも悪くはないが、ますますバカらしさが募り、授業もレポートもゼミも茶番でしかなくなるだろう。親からもいい加減にしろと怒られ、仕送りも止められ、わたしは生きるために風俗で働くしかなくなる。正直の息子さんも大きくなり、高校生になって正直の言うことを全然聞かなくなり、家庭内暴力を振るうようになり、家の中がめちゃくちゃになって離婚なんて空気ではなくなる。もう終わりだね。君が小さく見える。正直がそんなことを言い出し、そのまま自然消滅してわたしは金なし風俗オババになる。
大学の中に議論をするサークルっていうのがあって、大学生たちが何の責任もなく、ああでもないこうでもないとまるで現実的でないことを言い合うことに時間を費している。言い合った後はいつも飲み会があって、酒を飲んで飲んで酔って酔って酔っ払って、なにもかも分からなくなってその中の一人と寝てしまうこともある。この場合寝るというのは眠るという意味ではなく、セックスするということで、居酒屋の堀炬燵の中でことに及んだり、わたしの家のベッドでしたりする。性欲を掻き立てられた男とは、基本的にする。もちろん正直との関係もある。しかし、抗えないパターンが多い。流れができて、そういうモードになって、する。男たちはたいてい中出しをしたがって、わたしもいざその時になると中に出してもらいたくなるからそのまま受け入れちゃって、いつ妊娠するか分からなくてもうそれは恐怖でしかない。
いったいわたしは何をしているのだろう?
ふと我に返って、わけが分からなくなってそう思って死にたくなる時がある。正直は結局離婚も結婚もしてくれないだろうし、わたしはどんどん年を取って、そのうち仕送りも止められる。バイトなんてどれも長続きしなかったし、お金がないと生きていけないからもう死ぬしかない。でもわたしに死ぬ勇気なんてない。何度か試したけどダメだった。だから生きているしかない。生きているしかないのだが、生活は仕送りに頼っているからそれをずっと継続してもらうしかない。でもこんな暮らしがずっと続けば、わたしの頭はどうかしてしまう。脳がふやけ切って白子みたいになってその水分が抜け出て鼻をかんだ後のティッシュを丸めたものみたいになって、何も考えられなくなり、そこらじゅうの男たちに見境なくやらせまくって性病になってその毒が脳にまで回り、頭がおかしくなって死んでしまうだろう。
3
コンビニでビールを買った帰りにポストを覗いてみると、こんなチラシが入っていた。
NPO法人ワーキングコーポレーション 学童クラブりく
職員急募! 子供たちの宿題をみたり、遊びの相手をしたりする簡単なお仕事です。
その他に時給やらシフト制で週二日からとか連絡先など書かれていた。一見した感じでは条件的には悪くない。

へぇ、学童か。聞いたことはあるけど、実態はよく知らない。共働きの親が放課後の子供を預けておくところ、くらいの知識しかない。
バイトでもしてみるかと思っていたところだったし、本当に子供たちの宿題をみたり遊びの相手をするだけだったら、わたしでもやれるかもしれない。わたし自身が性格的に子供なためか、昔から子供を相手にするのは嫌いじゃなかった。子供より、体面ばかり取り繕って嘘ばかり吐いている大人の方がよほど信用ならない。きっとわたしはいわゆる〝大人〟が嫌いなのだろう。大人的なものの拒絶の上に今のわたしが成り立っている。
ビールを飲みながらそのチラシを五分くらい眺めていたが、なんだか自信がなくなるというか、現実的に考えられなくなってやっぱりやめておくことにした。
NPOっていうのも最近やたら聞くけど、なんだかうさん臭い。営利目的じゃないってことだけど、だったら何を目的にしてるんだろう。とにかくよく分からないし、あまり関わりたくない。宗教とか絡んでるかもしれないし。
でも、とりあえずバイトでも始めてみるか。半年くらい前にコンビニのバイトを辞めて以来働いていない。あそこはひどかった。オーナーが加齢臭キツめのデブおやじでわたしのことをずっとエロい目で見てたし、従業員になにかと難癖をつけてきてやたらと威張り散らしていてキモくなって一週間で辞めた。その前が牛丼家。入って四日目くらいに、熱々のお茶を運んでる最中に後ろから注文を受けて、振り返った拍子に手が滑って座って牛丼食べていたハゲのお客さんに頭からお茶をぶっかけてしまった。その人には謝り倒したが、でも心が完全に折れていて、具合が悪いからと早退してそれっきり。バイト経験はだいたいそれくらいで、もう働くこと自体が嫌になった。お金をもらうためにやりたくもないことを我慢して頑張る。それが働くということ。すなわち労働。なぜなら人間はお金がないと生きていけないから。働かないわたしが生きていけているのは、お父さんとお母さんが働いて得たお金を毎月仕送りしてもらっていて、携帯代も学費もここの家賃も光熱費も全部払ってくれているからだ。正直と結婚すれば、正直が働いて得たお金でそれらを払うことになる。わたしも働かなければそうなる。
お金、お金、お金、お金。
あぁ、お金さえこの世になければ、みんな幸せになれるのに。お金がみんなを苦しめている。お金がみんなを不幸にしている。諸悪の根源。世界中の人たちがこれに振り回されていて、みんながみんな不幸になっていく。

そんなことを考えていると絶望的な気持ちになってきて、わたしは誰かと話したくなって目の前にあった学童クラブ職員急募の番号に電話をしていた。
「はい、学童クラブりくでございます」
ほぼワンコールで男の声がそうこたえた。
「あのー、ちょっと働きたいっていうか、もう人生に絶望しちゃってて」
「はい? 絶望っていいますと」
「どの仕事してもぜんぜんうまくできなくて、彼氏ともウソだらけの関係で」
電話口の男はしばらく絶句した後、こう言った。
「たいへんご苦労なさってきたんですね。一度、その、面接がてらお話を聞かせていただけませんか。うちの事業所というかワーキングコーポレーションというNPO法人は、職員でそういう方もたくさんいらっしゃるというか、むしろそういう方ばかりでして」
「え、そうなんですか?」
「ええ」と男は答えた。「実はわたしもその一人で、いろいろとワケありでして」
「って言いますと?」
「いやいや、長い話です」
と言って男は軽く笑い、詳しくは面接の時に、ということになった。明日の十一時に面接を受けることになり、男は最後に広田と名乗った。
あぁ、宗教だな、と直感した。
宗教団体のフロント企業というやつだ。職員募集というテイを装って、行ったら宗教の勧誘をされまくる。集会へ来いだの偉い先生の講演会があるだの言われて、サクラだらけの密室へ連れていかれ、入信を迫られて入会書に署名捺印するまで帰れなくなる。
わたしは、学童クラブりく、でスマホで検索をかけてみた。
グーグルマップとホームページがヒットした。ホームページの方に行ってみると、子供たちが楽しそうに遊んでいる写真のバックに、学童クラブりく、というロゴが浮かび上がっている。入室説明会のお知らせやら学童保育の方針やら無難なお題目が並んでいて、その下にブログのページがあったから覗いてみた。
クリスマス会や新年会、芋掘りなど楽しそうに職員と子供たちが戯れている写真が短いコメントと共に掲載されている。
あれ? と拍子抜けした。普通じゃないか。
おかしいな。変な儀式の様子とか偉い先生のデカい顔写真とか長ったらしい肩書きとか講話なんかが載っているかと思ったのに。
いやいやいやいや、これはこれ。
今度はワーキングコーポレーションで検索してみた。
パステルカラーがまぶしいトップページが表われ、沿革やら運営方針やら、協同労働とか協同組合とかなんかよく分からない小難しい文言がだらだらと書いてあった。
宗教っぽくはないが、そういう予防線を張っているだけかもしれない。いや、よく分からない。なんだかとにかくよく分からない。
ためしに面接だけ行ってみようかな、と思った。さっき伝えた電話番号もデタラメだし、履歴書を持ってこいと言っていたが、そんなものを提出したら個人情報だだもれで、ばんばん電話がかかってきて出なかったら家まで押しかけて来られそうだから、書いたんだけど家にうっかり忘れてきちゃった的な感じにしよう。なんとかの集いとかなんたら先生の講演会とかに誘われても行かなければいい。行きます、行きます、絶対に行きます、と約束して行かない。興味を持ったふりをして、前のめりを装って安心させ、行かない。

広田は慌ててわたしがさっき伝えた番号に電話をかけるが、適当に思いついた番号を言っただけだから、その番号は現在使われておりません、になるか、どこかの誰かにつながって、その人に開口一番もう集いは始まってるんですが、いまどこですか? もう時間過ぎてるんですけど、となじるが、あのー、どちら様ですか? と訊かれ、ようやく広田はその電話口の相手がわたしではないことに気づく。あの、すみません、失礼ですがお名前……? と聞いたところで児島だよ! と怒鳴られて電話は切られる。
いける、いける。それで大丈夫だ。名前は伝えたが苗字だけだし、吉田という苗字は全国ランキングでだいたい十位前後で、八十万人くらいいるらしいからほぼ匿名に近い。
あー、いいね。おもしろい。おちょくってやろう。新興宗教って、あんなバカげた話やら教義を信じ込ませるためにどう話を持っていくのか興味あるし。駅前とかで変なパンフレットみたいな新聞配ってたり、なんとか聖人がどうたらこうたらだのぶつくさ唱えているのを見てて、あの人たちの頭の中どうなってて、なにがどうしてああなったのだろうといつも思っていたからちょうどいい。
4
ジーパンにミッ〇ーのTシャツ、髪は後ろで黒ゴムでまとめてポニーテール、化粧は目元だけという自分史上もっともラフな格好でスマホのグーグルマップを見ながら行ったら、相手もジーパンに黒Tにジーンズ地のエプロン、つんつん立った伸びかけの坊主頭という負けず劣らずのラフな感じだった。ひどく痩せていて、目が大きく背が高い。年はだいたい四十くらいといったところだろうか。
「じゃ、ちょっとそちらへ」

部屋はだいたい二十から二十五畳くらいで、壁際の棚におもちゃとかレゴブロックなんかが置いてあって真ん中ら辺に低いテーブルがいくつかとテレビが置いてある。
左奥のテーブルに案内され、わたしは広田と向かいあって座った。
「こちらの責任者をさせていただいております広田と申します」
エプロンについた名札をつまんでわたしに見せながらそう言った。
「吉田です。よろしくお願いします」
わたしはそう頭を下げた。
「じゃ、すみません。履歴書を」
「はい」と私は頷き、自分のトートバッグの中を漁った。
「あれ? あれあれあれ?」
「どうされましたか?」
「ない。え?」
さらに焦ったふりをしてがさごそまたバッグを漁る。
「書いたのに。昨日の夜書いたのにー!」
「あ、忘れてきちゃったんですかね?」
「あっ、もう! あそこだ。テーブルの上!」
そう言ってわたしは頭を掻きむしり、目を閉じて長いため息を吐いた。
「あ、じゃあ今度でいいです。履歴書はまあ、しょせん履歴書なので」
「すみません。取りに帰るとか……」
「あ、いいですいいです」と広田はかぶりを振った。「お話を聞ければあれなので。でも事務的なのでいるので、まあ、今度で。ご縁があればというまあ、そういうあれですが」
わたしは「すみませぇん」と言って、広田の顔をじっと見る、イケメンでもブサメンでもない。マスクで顔の下半分が隠れているから微妙だ。
「じゃあ、どうしましょうか。一応面接ってことなので、まずはこちらからここのお仕事のざっとしたことをお伝えしましょうか」
広田はあしを崩しかけてやめて、背筋をピンと伸ばしながらそう言った。
「あ、はい」と、わたしは頷く。

「まあ、ホームページとかもご覧になっているか知りませんが、まあいわゆる学童です。子供のことを見るのが仕事の九割です。見るっていうのは、怪我や喧嘩をしないように見守ったり、宿題の分からないところを教えてあげたり、遊びの相手をしてあげたりという感じです。あと、掃除とかお迎えとか事務的なこともありますが、まずは子供を見るということですね。それが主な仕事内容になります」
「見る……、ですか」
「ええ。話を聞いてあげるっていうのもあります。相手をすることですね。ここは家と学校の中間的なところですので、親御さんたちが迎えに来るまでお父さんお母さんや学校の先生の代わりに子供たちを『見る』んです」
分かったような分からないような説明だ。
「まあ、やってみりゃ分かります。っていうか、やってみないと分かりません。習うより慣れよってやつですね。以上です」
「はあ」とわたしは答え、マスクの上の広田の目を見た。
「じゃあ、次は吉田さんの番です。絶望したとかそういうことをお電話では仰られていたかと思うんですが」
ああ、そんなこと言ったかな。
「え、まあ、っていうかわたしもうすぐ結婚するんです」
すると、広田は頭をのけぞらして大袈裟に驚いた。
「えっ、あっ、おめでとうございます」
「あっ、は、ありがとうございます」
わたしは小さく頭を下げる。
「え、じゃあなんで絶望なんですか? ご結婚とか幸せじゃないんですか?」
「あー、まあちょっとワケがあって、っていうのはその彼には奥さんと息子さんがいて、でもその奥さんとはだいぶ前からうまくいってなくて、もうすぐ離婚して、わたしも大学卒業するからそのタイミングで結婚しようってことになってるんです」
「えっ、ああ、大学生なんだ」
フリーターかなにかと思っていたようだ。
「そう、でも離婚してくれるかどうか微妙で、わたしも大学ぜんぜん行ってないから、五年生になるの確定で、五年生で卒業できるかどうかも微妙で六年生になっちゃうかもしれなくて」
「離婚するか微妙ってことは、嘘吐いてるかもしれないってこと?」
「はい」と私は正直に頷いた。

「お互い嘘吐きあってるんです。ひどいですよね。なんなんですかね、人間って」
すると、広田は笑った。
「じゃあ、嘘吐かなきゃいいじゃん。少なくとも吉田さんはさ」
「好きで吐いてるわけじゃないですよ。吐かざるをえないから吐いてるんです」
「そうなんだ。相手が望む答えを言っちゃってるってこと?」
ああ、そういうことか。
「まあ、好きだし、嫌われたくないから」
こいつは何にも分かってないなと思いながら、わたしはそう答えた。
「え、でもずっと嘘吐き続けるわけにはいかないでしょ。いつかは本当のことというか地を出さなきゃいけなくなる」
んなことは、あんたに言われなくても分かっている。
「できないから悩んでるんです。できたら、とっくにやってますよ」
すると、広田はぴくりと眉毛を動かし、眉間の間に皴を作った。
「それもそうですね。失礼しました」
結局その場で採用ということになり、とりあえず週三日、人の足りない月、水、金の二時から六時の勤務とシフトまで決まった。
大学の方は大丈夫なのと訊かれたが、行ってないから大丈夫と答えた。
「でも、卒業するんでしょ?」
「分からないです。もう、心が折れちゃってるんで」
すると、フッと鼻で笑われた。
「じゃあ、辞めちゃえばいいじゃない」
「いえ、そうすると仕送り止められちゃうんで」
「あ、そっか。じゃあ続けなきゃだね」
案外、ものわかりのいい人のようだ。
詳しくは来週の月曜で、と話に片がつき、わたしは「りく」を後にした。
コンビニでツナマヨおにぎりとレタスサンドを買って帰り、それらで腹を満たしつつ、履歴書はどうしようか、そもそも来週の月曜からお願いしますと言っちゃったが、本当に行くのかどうかとかをぐるぐる考えた。
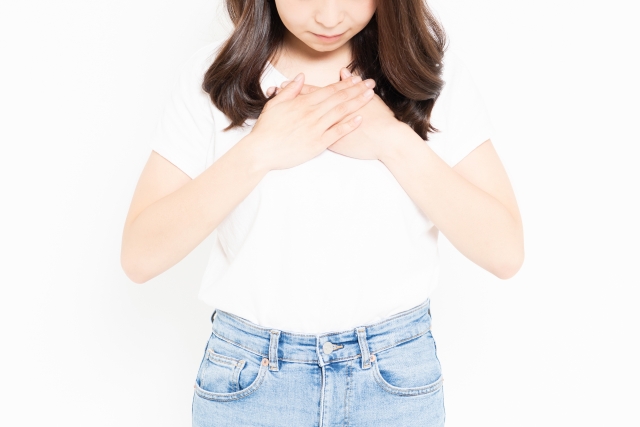
あの広田という男が信用できるかどうかは微妙なところだった。面接中もわたしの胸元を幾度となく見ていたし、帰り際靴を履くときには突き出した尻を超ガン見していた。きっと頭の中はエロいことでいっぱいで、さっそくわたしも今晩のオナニーのおかずにされることだろう。
でも、エロいからといって悪い人なわけではないし、エロいかエロくないかというより、隠すのが上手いか上手くないかの問題な気もする。広田は、上手くないを通り越して下手だ。あれでは大抵の女が気づく。あ、こいつ見てるぞ、と。あれでもうちょっと不細工かキモデブとかだったら、女は絶対に近づかないだろう。顔とスタイルがそこそこだから、まあいっかということでそれで生きてこられた。そう考えると外見というのはやはり重要なんだなと思う。同じことをしても、OKかNGかは外見で決まる。
まあ、いっか。履歴書はずっと忘れ続ければいいし、行くか行かないかは当日の気分で決めよう。
──バイトすることになったよー。来週の月曜から。
わたしはさっそく正直にラインを送った。十五分後に既読がつき、返事がかえってきた。
──え、ほほちゃんが? なに? どこ?
バカにされているような気もしたが、そんなことは気にしない。
──近所の学童。「りく」ってとこ。
──学童? なにそれ?
世代的に知らないのだろう。
──放課後の小学生預かるところだよ。共働きの家の。
──へー、よく知らないけど。っていうか大学もう大丈夫なの?
わたしは間を置かずこう打ち込んだ。
──うん。もう単位取り切ってるから大丈夫。今年は微妙だけど、来年は卒業できると思う。
既読がなかなかつかず、それは通知だけを見て既読をわざとつけずに考えているのだなと分かる間だった。その隙にわたしはトイレに行き、やけに黄色い小便が出てすっきりしたところで返事がかえってきた。
──じゃあさ、ほほちゃんが卒業したら離婚するよ。そしたら晴れて結婚すりゃいいじゃん。

返事を打てずに呆然としていると、続けざまこう送られてきた。
──それでみんなハッピーだよ。
わたしが卒業できないことを見越して、面倒なことを一気に片付けにかかっているのだ。いまの性生活と危ないゲームを続ける関係を保ちつつ、自分は実害を受けないところまで避難する。
──そうだね。ウィンウィンだね。
と、わたしは送った。
──じゃあ、それで。 来週からのバイトがんばってね。
──うん、ありがとう。
バイトどころではない。卒業しないと離婚も結婚もなくなってしまった。その結構重大な約束をいまラインでしてしまった。
バカなんだよな。わたしってほんとバカなんだよ。死にたくなる。
入学できたんだから卒業もできるだろうと思うのだが、ぜんぜん行ってなくていま何がどうなっているのか分からないし、もう全部むちゃくちゃに踏み倒しちゃっているから、どうしようもないのだ。
わたしが卒業して、正直が離婚して、わたしたちが結婚する。
これは前々から正直が企んでいて、言い出すタイミングを見計らっていたのだ。オムツごっことかそんなことをやっている時点で、本気とか恋愛とか愛情とかそんなんじゃないことは分かり切っていたし、でもそんな変態的感覚を共有してるっていうのはやっぱりゾクゾクするし、それはどこまでいっても性欲でしかないのかもしれないけれど、それはそれで何が悪いのだろう。
5
前日に昼から飲み過ぎて、しかもその酔っ払った状態で近所の公園で会ったおじさんとヤリまくったおかげで夜八時には寝て、翌日の朝七時にぱっちりと目が覚めた。
おじさんの姿はもちろんなく、おそらく介護施設で働く奥さんと近所の保育園に通う娘さんの待つ家へ帰っていた。

冷蔵庫にあった牛乳をがぶ飲みし、歯を磨いてテレビを漫然と観た。ニュースが流れていて誰かがどこかで殺されたり、世界の遠い国で相変わらず内戦だか戦争が続いていたりした。知っていても知らなくてもどっちでもいいことばかりで、わたしにはまったく興味が持てなかった。どこで誰が死のうが殺されていようが、うちの冷蔵庫にある牛乳の賞味期限の方がはるかに重要だった。それが悪いことだというのならば、そもそも人間という生物の成り立ちそのものに問題があるのだ。
十二時くらいまでスマホで動画を見ながらテレビも見ていて、一時にバイトの初シフトが入っていたことに気づいた。ああ、ダルいし面倒くさいな、と思ってブチってやろうかと考えた。でも、あの広田という男のエロい視線を思い出して行きたくなった。おっぱいも尻も半分出ているような恰好で行ってやったら、あいつはきっと仕事どころではなくなる。とても面白そうだ。
クローゼットから公道を歩くのはどうかと思われるほどのほぼ下着に近い恰好の服と、お辞儀をしたらパンツが見えてしまうスカートを出してきて着替え、黒いロングコートを羽織って家を出た。
一時五分にりくに着き、「遅れてすみませぇん」と息を切らしている振りをして駆け込むと、広田は時計をちらっと見て、「ああ、大丈夫です」と不満そうに言った。
「すみません。上着と荷物どこ置いたらいいですか?」
「あぁ、じゃあこっちの倉庫の方で」
天井の低い荷物置き場のようなところに小ぶりの冷蔵庫が置かれていて、奥のカーテンで仕切られた先に黒いリュックサックが置かれていた。
「コートとか上着はここにかけてください」
突っ張り棒が横の棚と奥の段ボールの間に渡してあって、そこにハンガーでファーのたくさんついたダウンジャケットが引っ掛かっていた。
わたしはカーテンの奥でコートを脱いでハンガーに吊るし、持ってきたハンドバッグの中から柑橘系の香水をわきの下に吹きかけた。
「お待たせしました」

カーテンを開けて出て行くと、倉庫の入り口のところに広田は立っていて、ごくりと唾を呑み込む音がはっきりと聞こえた。
「え……、え、エプロンは?」
「エプロン?」
「あ、すみません。エプロンってお伝えしてませんでしたっけ?」
聞いたような気もしたが、よく覚えていない。
「聞いてません。いるんですか?」
「あ、はい。仕事中は基本つけてる感じなので」
広田のエロ熱い視線がむき出しの胸の谷間や肩や脚に注がれる。
「……予備わたし持ってるんで、今日はそれをお貸しします。…で、ちょっとっていうかもうちょっと大人しめな恰好で来ていただけると助かります。三、四年生とか高学年の男の子とかもいるんで」
それよりあなたですよね、という気もしたが、あ、はいと無難な返事をしておいた。
カーキ色のカフェ店員のようなエプロンを広田は倉庫から引っ張り出してきて、わたしに手渡した。名札は別のところで作るので、頼んでおきますと言われた。
上からかぶる方式のエプロンで、着ると下着のような服やマイクロミニのスカートが完全に見えなくなり、裸エプロンのような感じになった。
「おっ、うーむ!」
わたしの裸エプロンを見た瞬間、広田はそう言って唸った。
「なんかめっちゃエロいっすね。……ヤバ」
何でも正直に言う人のようだ。本当に困っている様子だったから少し気の毒になった。
「AVみたいですよね。ごめんなさい」
「あ、うん。今度からお願いします」
広田もエプロンをつけているせいで、股間がどうなっているのかは見えない。だが、腰が引けているところを見ると反応はしているのだろう。
「じゃあ、はじめましょうか」
「はい、よろしくお願いします」
わたしは元気よくそう答えた。
6
「で、ここにその変な消毒液みたいなのを薄めたやつが入ってるので、それを加湿器のここへ入れてください。一本分入れても足りないんですけど、まああとは水を水道からこうじゃーっと入れてここらへんまで」

広田は実際にやってみせながら、そう話をして、白い蓋をかぶせた。
「で、こっちの透明な窓がある方を前にしてスチャッと入れて、こぼさないようにこっちに持ってって、ピッと電源を入れます。コースは自動で。これでOKです」
すぐに蒸気が吹き出し口から出始めた。
「夏もこれやるんですか?」
「ええ、私的にはいらないと思うんですが、所長からやれって言われるので」
なんでも出水所長というのが絶対権力者として君臨していて、広田もその人には逆らえないらしい。
「意味分かんないですよね。冬とか湿度低い時はまあガンガン炊けばいいと思うんですけど、高温多湿な時に加湿器って私もちょっと理解できないんですよね」
そんなことをわたしに言われても。
「それでも、やるんですよね?」
「ええ、まあそういうことになってるので」
広田は顔を顰めながらそう答えた。
納得してなければやらなければいいのに。この人は自分の意志がないのだろうか。
トイレ掃除のやり方や掃除機のかけ方、業務日誌のつけ方などを教わっていると二時を回り、他のパートのおばさん、おばあさんたちが出勤してきた。
「ちょっと、そのエプロンヤバいよね。りひとくんとかがなんか言いそう」
太った落ち武者みたいな顔の高木というおばさんがわたしの身体を頭から下まで舐めるようにじろじろ見た後、そう言った。
「脱いどいた方がいいですか?」
「いやいや、脱いだらもっとヤバいっしょ。わたしのパーカー貸すから、とりあえずそれ着といたら」

荷物置き場のハンガーに掛かっていたくすんだ灰色のパーカーを、わたしに手渡す。汗臭くて着たくなかったが、たしかにこんな格好で子供に接すれば、親からクレームが来るだろう。
「下はしょうがないよね。タオルでも巻いとく?」
「いや、風呂上がりみたいになって、よけいヤバいっす」
広田が実感のこもったツッコミを入れた。
「りひとくん気をつけてね。あの子、男の子っていうか、男だから」
「男ですか?」
「そうそう。ボーイじゃなくてマン。身体も大きくて性欲はバリバリあるんだけど、子供だからってセクハラ的なことが許されてるってすごい状況なんだよね。まあ、こっちは許さないんだけど、親御さんの手前言い出しにくくって」
たしかにすごい状況だ。
「ま、とにかく気をつけて。脚とかどっか触ってきたら言って。注意するから。膝とか乗ってくるかもしれないし」
もう、むちゃくちゃだな。歌舞伎町のお触りパブかよ。
8
落ち武者高木と一緒に、歩いて五分くらいのところにある小学校へ子どもたちを迎えに行った。
「そういう格好好きなの?」
「あ、はい。見られてるっていうのが快感で」

「それな。承認欲求ってやつだよね。自己評価が低い人ほどそうなるんだって」
なに言ってるんだろう。この人は。
「へー。そうなんですね」
「あたしなんか、それ以前に女として見られないから最悪だよ。あたしがそんな恰好したら、もうみんなから笑いものだよ」
たしかに、想像もしたくない。
「まあ、無難な恰好しといたほうがいいよ。親御さんも子供も色んな人いるし。変な噂たてられたりしたら、吉田さんも嫌でしょ」
「ジーパンとかですか?」
すると、高木は振り返って小刻みに頷いた。
「そうそう。夏はジーパンにTシャツ。冬はセーターかタートルネック。みんなGUかユニクロかしまむら。安いし」
「それだとつまんなくないですか。個性が出せないっていうか……」
「そんなの、個性なんか出さなくていいの。そういうのはおうちの中か休みの日に原宿か渋谷行ってやって。ま、仕事っていうか学童だからね」
釈然としないものが残ったが、とりあえ頷いておいた。
学校に着くと、子どもたちがすでに集合場所とされるところで待っていて、さんざん遅いー、とかなにやってんの! とか好き放題言われた。
「学校から貰った表には二時四十分って書いてあったんだって! 今三十七分でしょ。遅れてないっつーの!」
聞くと、よくあることのようだ。帰りの会が早く終わって予定時間より早く出て来たり、逆に長引いて待ってても全然出て来なかったり。
「あー、なにこの人! 新しいせんせい?」
二年生くらいの小鹿のような目をした男の子がきいてきた。

「そうです。よしだです。よろしくね」
わたしは男の子の前にしゃがみ込んで、そう答えた。
「下の名前はなんていうの? おれ、たいち」
「ほほです。よしだほほ。たいちくんの上の名前は?」
つい本名を言ってしまった。
「…えんどー」
それだけ小さな声で言い残し、もうこの会話に耐え切れなくなったのか、そっぽを向いて他の子のところへ行ってしまった。
「へー、ほほっていうんだ。ひらがな?」
横で聞いていた高木がきいてくる。
「いえ、船の帆の帆にカタカナのノマって繰り返すマークです」
立ち上がりながらそう答えると、一、二年生くらいの肌の浅黒い、割と背の高い女の子が「ほほちゃん、ほほちゃん」と連呼した。
「こら、ほほちゃん先生でしょ」
と、高木がたしなめたところでわたしの呼び名が決まった。
ほほちゃん先生。
語呂も響きもいい。先生なんて今まで呼ばれたことがなかったから、虚栄心と承認欲求がくすぐられて何だか気持ちもいい。
「あなたはなんて言うの?」
「よしか。さいきよしかです」
またしゃがみ込み、よしかちゃんの目をまっすぐ見る。
「よしかちゃんか。みんなからは何て呼ばれてるの?」
「よっちゃんとか、よっしーとか」
「よろしくね。よっしーちゃん。わたしほほちゃん」
すると、よしかちゃんは笑って「よっしーちゃんって!」とツッコんだ。
高木が持ってきていたお迎えリストで全員いることを確認し、二列に並んで小学校を出発した。高木が先頭。わたしが一番後ろ。

後ろの方には三、四年生がいて、その中に話にも出ていたりひとくんも混じっていた。背が高くて小太りで、マリオのTシャツを着ている。
「え? っていうか、それ下なんも履いてないの?」
さすが子供。どストレートな質問が飛んできた。
パーカーとエプロンを捲って、黒のミニスカートを見せる。
「履いてます。ちょっと短いけど」
「え? っつーか、短か! ちょっともう一回見せて」
これはもう子供じゃなかったら立派なセクハラだ。
「いやです。服間違えちゃったの!」
変に気をつかったりすると舐められる。で、それがだんだんエスカレートしていく。今まで散々学んできたことだ。
「見せてよー。ほほちゃーん」
ウザ絡みだ。こんなもの相手が小学四年生じゃなかったら、即現行犯逮捕だ。このやろーが。完全にエロい目で見てるし、自分の立場を利用してやがる。
「は? キモいんですけど」
冷ややかな低い声でそう答えた。すると、りひとくんは一瞬目を泳がせたが、その目をじっと睨みつけてやった。
「女の人にそういうこと言っちゃだめでしょ。りっくん」
そばにいた顔立ちの整った美少女がそう言ってまとめてくれた。
「ありがとう。えーっと…」
「れいらです。剣持れいら。みんなからはれいちゃんって呼ばれてます」
「ありがとう、れいちゃん」
りひとくんはれいらちゃんを憎々しげに睨みつけていた。さすが子供。あからさまだった。
「しねっ」
そう呟き、鼻であざ笑うのをわたしは見逃さなかった。
学童に着くと、わあわあ騒ぎながらみんな宿題をして、その後おやつを食べ、遊びに巻き込まれていった。

妖怪ボードゲームとかいうのが流行っていて、わたしはぬらりひょん役をやらされ、手下の妖怪カードを集めたり取られたりしながら、三番目にゴールした。ちなみに四人でやっていたからビリだった猫娘役のちかちゃんという一年生の女の子は、テーブルに突っ伏してこの世の終わりのように泣きだした。わたしが集めたぬりかべやかまいたちをのカードあげて機嫌を取ろうとしたが、無駄だった。顔を上げようともしない。
高木に経緯を話すと「先生とちょっとお話しよ」と事務所に連れていき、そこで何か話をしばらくしていた。そして、高木と一緒に出てきたときにはちかちゃんはなにかが吹っ切れたような顔をしていた。
「すみません。気をつけます」
わたしがビリにならなければならなかったのだと反省し、高木にそう言った。
「ううん。先生はいいの。負けることができるようにならなきゃねってそういう話をしたから」
それで子供は納得したのだろうか。
「いいんですか? 勝っちゃって」
「わたしはいいと思う。負けを受け入れるってすごく大事なことだと思うから」
負けを受け入れる。
「よく誤魔化したりズルしたりして勝とうしたり、負けそうになったらやーめたってどっか行っちゃったりする子いるの。あれ、良くないんだよね。負ける時はしっかり負けないと」
しっかり負ける?
「へぇ、そうなんですか」
「そうそう。負けてその負けをいったん受け入れないと、次進めないで──」
「ね、先生。ほほちゃん! パズルやろーよ」
さっきまで泣いていたちかちゃんがそう言ってわたしの袖を引っ張った。
「こら、ほほちゃん先生でしょ!」

高木がすかさずそう注意した。ちかちゃんの顔を見ると、そこにはもうさっきまでのこの世の終わり的な表情はなく、楽しくて仕方がないといった顔になっていた。さすが子供。
スペインファミリーという今人気が出てきているというアニメのジグゾーパズルをまあさちゃんという三年生の大人しそうな子も交えてやっていると六時になり、出していたおもちゃを子供たちと一緒に片付けているところで、広田に声を掛けられた。
「お疲れ様です。定時なので上がってください」
「あ、はい」
広田の顔には疲労が色濃く滲んでいた。
「どうでしたか?」
「いやぁ」とわたしは首をひねりながら答えた。「よく分からないですね。子どもっていうのがまだよく分からないです。今日もうまくやれたんだが、どうなんでしょ」
「けっこううまくやれてたと思いますよ。ちょっと見てましたけど」
「そうですか。でもちかちゃん泣いちゃったし」
「ああ」と、広田は訳知り顔にうなづいた。「あれはあれでいいんですよ。高木先生がフォローしてたし。感情がストレートに出せてるってことだからいいんじゃないかな」
何を言っているのかよく分からない。
「あ、はい。ありがとうございます」
とりあえずそう礼を言って頭を下げておいた。
倉庫のカーテンの奥でエプロンを脱ぎ、残っている職員と子供に挨拶をして黒いコートを羽織って外に出た。

星がとてもきれいな空で、ちょうど半分に欠けた月が低い位置に浮かんでいた。
自分の家に向かって歩いていたら、数分前まで自分がしていたことの感覚がすーっと薄くなっていった。異世界にワープしていたような感じで、コンビニに入ってストロングゼロと鮭おにぎりとポテチを買ったらいつもの現実にしっかり戻ってこられた。
帰り際、広田には次は水曜でと言われていたから、つまり明後日ということになる。明後日にまたあそこに行けば、異世界転生することになる。
あぁ、面倒くさいな。しんどいし。泣いたりわめいたりセクハラされたりするし。
子供ってああいうものか。かわいいとか天使とか言っちゃったりする人多いけど、しんどくて面倒くさい部分の方が大きい。
でも、あれみんな本音だよな。本音隠していい子演じる子もいるだろうけど、泣いたりわめいたりワガママ言ってる子たちはみんなあれ本音が炸裂してるだけなんだろうな。大人も普段生きていて同じようなこと思ったり考えたりしてるんだろうけど、プライドとか体面とかがあるから本音を炸裂させてないだけなんだよね。そういう意味では分かりやすい。大人より分かりやすい。だって、まんま出てるし。見りゃ分かるから。
大人はオブラートに包んで隠してるけど、子どもはむき出し。むき出しの人間。
料理でいうと刺身だ。切って盛って出すだけ。新鮮なうちは美味しいけど、時間が経つとマズくなって、そのうち腐って食べられなくなる。
自宅マンションに帰ってポテチを食べながらストロングゼロを飲みつつそんなことをつらつらと考えていると、なんだか子どももそんな悪くないような気がしてきた。わたしとよく似ている。天ぷら粉や揚げたパン粉や味噌や溶いた卵に包まれたりせずに、刺身で生きている。
むき出しのまま生きる。
はだかエプロン。
セクハラにはブチ切れる。
泣きわめいたら、うっせえわ!
ほほちゃんはそう誓い、ストロングゼロを飲み干しましたとさ。
[了]